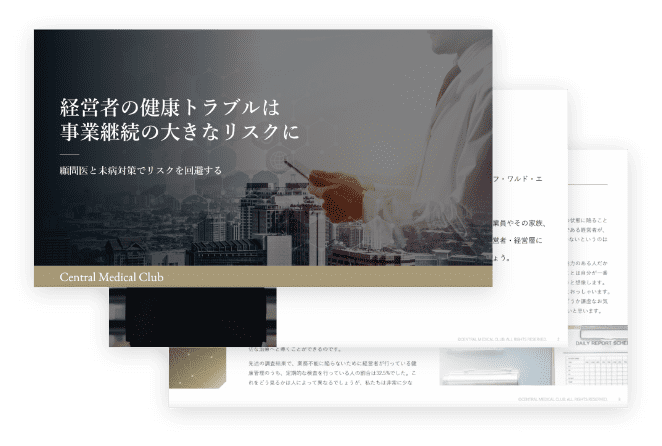脳ドックは何歳から受けるべき?受けた方がいい人の特徴やメリット・デメリットも解説

近年、人間ドックで受診できるコースやオプション検査は幅広くなっています。健康管理に気をつけている方ほど、脳ドックという言葉を見たりおすすめされたりした経験があるのではないでしょうか。
しかし、人間ドックは基本コースだけでも検査項目が多いため「本当に今必要なのだろうか」「何歳から受けるべきだろうか」と悩んでしまいますよね。
そこで今回は、脳ドックの受診に適した年齢や、受けた方がいい人の特徴、メリット・デメリットになどについて解説します。
脳ドックとは?検査でわかること

脳ドックは、MRIやMRAといった機器を用いて脳の状態を詳細に調べる検査です。自覚症状の出にくい脳の病気を、早期発見・予防することを目的としています。
脳の病気には、脳腫瘍や脳血管疾患(脳の血管に異常がある病気の総称)などがあり、脳血管疾患のうち、急激に発症するものは脳卒中(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞)とよばれます。
脳卒中は、一度発症すると後遺症が残ったり、命に関わったりする重篤な疾患です。脳ドックでは、脳卒中リスクを早期発見し、発症を予防することが最大の目的となります。
脳ドックで分かる主な疾患として以下が挙げられます。
- ・脳卒中
- ・脳腫瘍
- ・脳動脈瘤
- ・頸動脈梗塞
- ・認知症
など
脳ドックが必要な理由

厚生労働省の「人口動態統計(確定数)の概況」によると、脳血管疾患による死亡は、令和5年の死亡者数全体の6.6%を占めており、悪性新生物(がん)、心疾患、老衰に次ぐ4番目に多い数字でした。
脳血管疾患は、決して他人事ではないといえるでしょう。
参考:厚生労働省ホームページ「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」
脳卒中は脳細胞や神経細胞にダメージを与えるため、たとえ一命を取り留めても、麻痺や言語障害などの後遺症が残ることもあります。日本における介護原因では、脳血管疾患は、認知症に次いで2番目に高い割合を占めています。
参考:厚生労働省ホームページ「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」
しかし、一般的な人間ドックでは脳の血管を専門的に検査する項目はなく、脳の病気を発見することは難しいとされています。治療の遅れによる後遺症を避け、家族への介護負担を軽減するためにも、脳の検査に特化した「脳ドック」で異常を早期発見することが非常に重要なのです。
脳ドックは何歳から受診すべき?

脳ドックを受診すべき年齢として、40歳以上の人は積極的に検討するとよいでしょう。なぜなら、脳血管疾患による死亡率は20代後半から高まり、40代になるとさらに増加するからです。
40~54歳の死因の第4位は脳血管疾患です。55歳~84歳では死因の第3位となっています。40歳以上で一度も脳ドックを受けていない方は、受診を強くおすすめします。
20代後半から30代の若い世代でも、脳血管疾患は死因の第5位となっています。死亡率としては死亡数全体のうち0.7~4.1%と高くはないものの、脳血管疾患のリスクのある方は、若い世代でも脳ドックを受診しておくと安心です。
特に、次に紹介する脳ドックを受けた方がいい人の特徴に当てはまる方は、脳ドックを受診しましょう。
参考:厚生労働省ホームページ「令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況」
脳ドックを受けた方がいい人の7つの特徴

脳ドックを受けた方がいい人の7つの特徴として、以下が挙げられます。
- ・40歳以上の中高齢者
- ・脳卒中・認知症の家族歴がある方
- ・肥満気味の方
- ・高血圧・脂質異常症・糖尿病の方
- ・喫煙習慣のある方
- ・日頃から頭痛のある方
- ・脳ドックを受けることで安心感を得たい方
それぞれについて以下に解説します。
40歳以上の中高齢者
40歳以上で一度も脳ドックを受診したことがない方はもちろん、脳ドックを受診したことがある方も、中高齢者は定期的に脳ドックを受診することをおすすめします。
厚生労働省の令和5年(2023年)患者調査によると、脳血管疾患の推計患者数は男性では75~79歳、女性では90歳以上が最も多くなっています。くも膜下出血については、男性では55~59歳という比較的若い世代でも70~74歳と並び、推計患者数が最多です。
参考:e-Stat「患者調査 / 令和5年患者調査 / 全国編」
特に50代以上の中高齢者では、脳血管疾患のリスクが高まります。脳ドックを定期的に受診しましょう。
脳卒中・認知症の家族歴がある方
家族に脳卒中や認知症の方がいる場合、脳ドックを積極的に受診するとよいでしょう。
なぜなら、家族に脳卒中や認知症の方がいる場合、ご自身も脳卒中や認知症を発症するリスクが高くなるからです。
特に、くも膜下出血は家族歴との関連性が深いことが分かっており、家族歴がない場合の未破裂脳動脈瘤(脳血管がこぶ状にふくらんだものが破裂していない状態)の有病率が3~5%なのに対し、3親等以内にくも膜下出血の家族歴がある場合の有病率は20%近いといわれています。
くも膜下出血の原因の約75%は、脳動脈瘤の破裂だといわれています。3親等以内にくも膜下出血を患った方がいる場合は、脳ドックの受診を強くおすすめします。
肥満気味の方
肥満度の高さは、脳卒中の発症リスク上昇と関連があることがわかっています。肥満気味の方は、適正体重を目指すとともに、定期的に脳ドックの受診を検討しましょう。
高血圧・脂質異常症・糖尿病の方
高血圧・脂質異常症・糖尿病の持病がある方は脳卒中になりやすいといわれています。日本人においては、特に高血圧との関連性が深いことが分かっています。これらの診断を受けたことがある方は、脳ドックを受診するとよいでしょう。
喫煙習慣のある方
喫煙習慣のある方は、脳ドックの受診をおすすめします。
喫煙者は脳卒中になりやすいことが分かっているからです。「喫煙者は、非喫煙者にくらべ、男性で1.3倍、女性で2.0倍、脳卒中になりやすい」という報告もあります。
参考:国立がん研究センターがん対策研究所「男女別、喫煙と脳卒中病型別発症との関係について」
喫煙習慣のある方は、脳ドックを受診するとともに、禁煙をこころがけることが脳卒中の予防につながるでしょう。
日頃から頭痛のある方
日頃から頭痛のある方は、脳ドックを受診し、脳腫瘍や脳出血などの脳の病気や、脳の血管に異常がないかを調べておくと安心です。
頭痛はよくみられる症状の一つであり、自然におさまる軽症のものもありますが、なかには命に関わる重大な病気が隠れている場合もあるからです。
また、片頭痛がある方は、脳梗塞や認知症の発症リスクが高くなるという研究報告があります。片頭痛と診断されたことがある方も、脳ドックを定期的に受診するとよいでしょう。
脳ドックを受けることで安心感を得たい方
脳ドックを受けることで安心感を得たい方は、脳ドックの受診をおすすめします。
脳ドックで異常が判明した場合、早期治療や生活習慣の改善につながります。異常がないことが分かった場合も、病気を心配するストレスを減らすことにつながります。
【年代別】脳ドックの受診頻度

脳ドックは、一度受診すればそれで良いというものではありません。脳の病気は自覚症状が出にくいため、脳ドック受診時にはなかった異常が徐々に進行し、ある日突然、命を落としてしまうような重大な疾患となって現れるケースもあるからです。
このような不幸な事態を避けるためにも、脳ドックは定期的に受診することが大切です。
では、脳ドックの受診頻度は、どの程度が適切なのでしょうか。以下に年代別脳ドックのおすすめ受診頻度を紹介します。
20代・30代におすすめの受診頻度
20代・30代の方は、一度脳ドックを受診して異常がなければ、40代以降に再度受診を検討するとよいでしょう。
ただし、若い世代でも遺伝的な要素や生活習慣によっては脳血管疾患を発症しやすい方もいます。脳ドックを受けた方がいい人の特徴に当てはまる方は、3~5年おきに受診しておくと安心です。
40代におすすめの受診頻度
40代の方は、脳ドックで異常がなければ、3~5年おきの頻度で受診するとよいでしょう。ただし、異常が見つかったり経過観察が必要と判断された場合は、医師の指示に従いましょう。
50代以降におすすめの受診頻度
50代以降は、脳血管疾患だけでなく認知症の発症リスクも高まります。脳ドックで異常を指摘されなかった場合でも、少なくとも2~3年おきに受診しましょう。異常が見つかった場合は、医師の指示に従いましょう。
脳ドックの5つのデメリット

脳ドックを定期的に受診することで、脳の病気やそのリスクの早期発見につながります。しかし、脳ドックにはデメリットも存在することを知っておくと良いでしょう。以下に詳細を解説します。
検査環境が負担になる場合がある
脳ドックの代表的な検査であるMRI検査は、頭から足までが覆われるトンネル型の機械に入って検査画像を撮影することが多くあります。現在では、頭部から肩以外部分は開放的となっている型の機器も多く導入されており、以前ほどは閉鎖感を感じにくい設計となっています。しかし、閉鎖的な環境が苦手な方にとっては負担となる可能性があるでしょう。
また、MRI検査はその仕組上で、どうしてもガンガンといった大きな音を伴います。音に敏感な方にとっても負担に感じる場合があるでしょう。
検査時間が長い
MRI検査の検査時間は、通常20~40分程度です。検査前の説明や体調チェック、着替えなどの時間も含めると、2時間程度を要します。忙しい方にとっては、検査時間の長さはデメリットに感じるでしょう。
しかし、これに関しては脳疾患を早期発見できるメリットのほうが大きいといえます。
造影剤によるアレルギーの可能性がある
脳ドックでは、検査時に造影剤を用いる場合があります。体質によっては、造影剤に対するアレルギー反応として、痒みやじんましん、くしゃみ、咳、吐き気などの症状があらわれることがあります。また、ごく稀な副作用として、呼吸困難や血圧低下などの重い症状が現れる場合もあります。
アレルギー体質の方や腎機能が低下している方は副作用が出現しやすいとされていますので、事前に医師に相談するとよいでしょう。
磁場酔いの可能性がある
MRI検査では、体が磁場に晒されることにより、めまいや吐き気、頭痛といった症状が生じることがあります。一過性の症状のため心配はいりませんが、磁場酔いの症状が引き起こされる可能性があることを知っておくとよいでしょう。
異常が見つかった際に心的負担となる可能性がある
脳ドックでは、過去に発症した脳梗塞が見つかることもあります。過去に脳梗塞を起こしていても、症状がなければ、多くは経過観察となります。
また、未破裂脳動脈瘤が見つかることもありますが、未破裂の状態では無症状です。そのまま破裂しないこともあるため、経過観察となる場合もあります。
このように、脳ドックでは、異常が見つかっても治療をせず経過観察となることがあります。人によっては、異常が見つかることで神経質になり、心的に負担がかかるかもしれません。
脳ドックの3つのメリット

脳ドックにはデメリットもあることをお伝えしましたが、もちろんそれらを上回るさまざまなメリットもあります。脳ドックの代表的なメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- ・脳の病気に関する異常を発見しやすい
- ・脳ドックで判明した疾患の早期治療ができる
- ・生活習慣の改善ができる
それぞれについて、以下に解説します。
脳の病気に関する異常を発見しやすい
脳ドックの最大のメリットは、脳の病気に関する異常を発見しやすい点です。
脳ドックに用いられるMRIやMRA、頸動脈超音波(エコー)、CTといった機器は、脳や関連する血管の様子を画像で写し出すことができます。脳の状態を画像でチェックできるため、異常を早い段階で検知することが期待できます。脳の異常を早期に発見できれば、生命に関わるかもしれない重大な疾患の発症を予防できる点については、大きなメリットであるといえます。
脳ドックで判明した疾患の早期治療ができる
脳ドックで判明した異常に対し早期治療をおこなうことは、重篤な後遺症の回避や、生命を救うことにつながる場合があります。
例えば、くも膜下出血の原因の約75%は、脳動脈瘤の破裂だといわれています。また、脳動脈瘤の破裂による初回のくも膜下出血で、約40%の方が命を落とすもしくは重い後遺症が残るといわれています。
脳ドックでは発見された脳動脈瘤を手術で取り除くことで、くも膜下出血発症リスクを抑えることができれば、重篤な後遺症や命を落とすリスクを回避できるでしょう。
その他、脳腫瘍を初期の段階で見つけられれば、早期治療により完治を期待出来る場合もあります。
生活習慣を改善できる
脳ドックで異常が見つかった場合、悪化しないように生活習慣を改善するきっかけとなるでしょう。例えば、喫煙をしている方は喫煙本数を減らしたり、塩分摂取の多い方は食生活を見直したりすることで、脳血管疾患の発症リスクを軽減できます。
多くのメリットがある脳ドックですが、受診を検討している方のなかには、費用、検査時間や選び方について気になる方もいるでしょう。
費用や検査時間、脳ドックの選び方など詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください。
まとめ ~脳の病気で後悔しないために~

脳ドックは、ときに命に関わる重大な疾患である脳卒中をはじめとした「脳の病気」のリスクを早期発見し、発症の予防や早期治療を目的とした検査です。
脳血管疾患は日本人の死因の第4位であり、決して他人事ではないといえるでしょう。脳血管疾患のなかには、一命を取り留めたとしても後遺症が残るものもあり、家族への介護負担を避けるためにも早めのリスクチェックが重要です。
脳ドックにはいくつかのデメリットもありますが、異常が見つかったことをきっかけに生活習慣を見直す良い機会となる等、多くのメリットがあります。脳血管疾患を発症してから後悔することのないよう、定期的に脳ドックを受けることをおすすめします。
40代以降の中高年者だけでなく、20代・30代の若い世代でも、脳卒中・認知症の家族歴がある方、肥満気味の方、高血圧・脂質異常症・糖尿病の方、喫煙習慣のある方、頭痛のある方などは脳ドックを受けると安心です。
リスクや年代に応じた最適な頻度で定期的に脳ドックを受診しましょう。