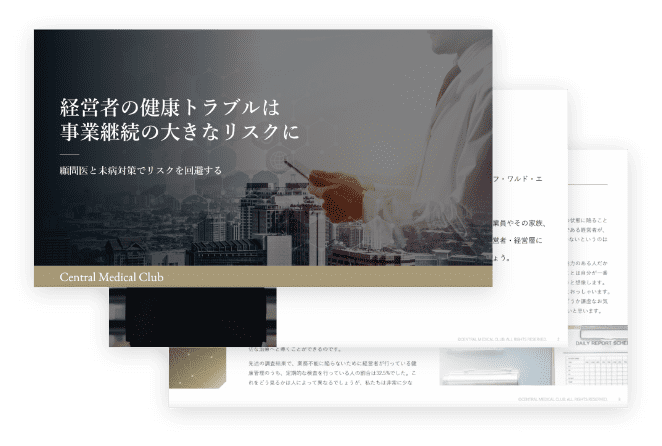認知症は早期発見・早期治療が重要!初期症状や検査方法など解説

超高齢化社会といわれる日本では、65歳以上の人口が増加しており、2023年10月1日時点で全体の29.1%となっています。それに伴い、ご自身やご家族の認知症について不安がある方も増えていることでしょう。
認知症は、前段階と考えられている軽度認知障害(MCI)も含めると、65歳以上の高齢者の約4人に1人が発症するとされている身近な病気です。しかし、進行を遅らせる治療薬は存在するものの、完治させる方法は確立されておらず、早期発見が重要となります。
そこで本記事では、認知症を早期発見・早期治療するために知っておくべき初期症状、検査方法、認知症になりやすい人の特徴などをわかりやすく解説します。
ご本人もしくはご家族に認知症を疑う症状があり病院を受診すべきか検討中の方や、認知症の初期症状を知って進行を予防したい方などは、ぜひ本記事を参考にしてください。
認知症を早期発見・早期治療することのメリット

「認知症は年のせいだから仕方ない」「治療法はなく完治が難しい」などのイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。しかし、認知症は脳の病気が原因で発症する疾患です。早期に発見し適切に対策することで、次のようなメリットがあります。
症状が改善する可能性がある
認知症の症状を引き起こす病気には、正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫、甲状腺機能低下症など、適切な治療により回復が期待できるものもあります。早期に正確な診断を受け、原因を突き止めることが大切です。
進行を遅らせることができる
認知症は診断が早ければ早いほど、高い治療効果を期待できます。
軽度認知障害の段階で適切に治療することで、アルツハイマー型認知症による認知機能の低下を遅らせる薬もあります。
今後の生活の準備ができる
認知症の早期発見により、ご本人やご家族が認知症への理解を深めるための時間的余裕が生まれ、今後の生活の備えができます。
ご本人の症状が軽いうちに、介護保険サービスの利用などについて話し合うことで、ご本人の意思を尊重することも可能となります。
適切なサービスの提供を受け、生活環境を整えることで、生活上の支障を減らすこともできるでしょう。
認知症の7つの初期症状

認知症は身近な病気であるにもかかわらず、「自分は大丈夫だろう」と思い込み、診断が遅れる場合も多いのが現状です。初期症状を理解し、早期発見に努めたいですね。ここでは、認知症の初期症状について解説します。
もの忘れ
認知症の初期症状としてよく知られているもののひとつに「もの忘れ」があります。しかし、「認知症によるもの忘れ」と、「加齢によるもの忘れ」は区別がつきにくく、判断が難しい場合もあるでしょう。
両者の見分け方として、「認知症によるもの忘れ」の場合、体験したことのすべてを忘れるが、「加齢によるもの忘れ」の場合、体験したことの一部を忘れるという例が挙げられます。具体的にいうと、朝ごはんを食べたこと自体の記憶がないのは「認知症によるもの忘れ」、朝ごはんのメニューを思い出せないのは「加齢によるもの忘れ」である可能性が高いでしょう。
判断力や理解力の低下
認知症の初期症状として、判断力や理解力の低下も挙げられます。
買い物のときに計算が難しくなったり、周囲との会話についていけなくなったり、電話をしながらメモをとるなど2つのことを同時にするのが困難になったりします。
集中力や注意力の低下
認知症では、集中力や注意力の低下がみられることもあります。
本や新聞を読まなくなったり、お金の管理に支障がでたり、家事や買い物に手間取るようになったりすることがあります。
時間や場所がわからなくなる
認知症では、時間や場所がわからなくなることもあります。
日付がわからなくなる、休日にもかかわらず仕事に行ってしまう、季節外れな服装で出かけてしまう、慣れた道で迷うなどの症状が出る場合があります。
性格の変化
穏やかな性格だった方が急に怒りっぽくなるなど、性格の変化が認知症のサインになることもあります。
不安症状
不安症状が認知症の初期症状としてあらわれる場合もあります。特に、アルツハイマー型認知症では、早期の段階から不安症状がみられるケースが多いとされています。
意欲の低下
認知症の初期症状として、意欲の低下がみられる場合もあります。
具体的には、ニュースなどに関心がない、趣味をやめてしまう、身だしなみに気を遣わなくなるなどが挙げられます。
認知症の検査方法

認知症を早期発見するためには、なるべく早く医師の診断を受けることが大切です。
認知症の検査には、主に「MRI検査」、「PET検査」「長谷川式認知症スケール」の3つがあります。
MRI検査
MRIで大脳の萎縮や血管障害、脳腫瘍の有無について調べます。
認知症は、脳が萎縮しているかどうかで決まるものではありませんが、極度な萎縮が発生しているために、記憶障害などの症状が起こっている場合もあります。
PET検査
PET検査と聞くとがん検診をイメージする方が多いかもしれませんが、認知症の早期発見にも有用です。認知症の診断におけるPET検査では、FDG・アミロイド・タウなどの成分の沈着を検出します。
アルツハイマー型認知症では、症状が現れるずっと前から脳にアミロイド沈着が始まり、次にタウ沈着や代謝や血流の低下、その後に脳萎縮が現れます。つまり、PET検査を用いることで、脳萎縮が始まる前の早期の異常でも診断できるのです。
PET検査についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
>>PET検査でアルツハイマー病の有無がわかるのは脳の細胞レベル(糖代謝)の様子がわかるから
長谷川式認知症スケール
長谷川式認知症スケールは、主に認知症の診断の補助的な検査として使用されます。評価項目への回答をもとに点数化し、30点中20点以下の場合、認知症の可能性が高いことがわかります。
評価項目は、年齢、日付、場所、3単語の復唱、計算などの9つの質問で構成されており、本人の生年月日さえ確認できれば実施できる検査です。所要時間は5~10分程度で、簡単に実施できるという特徴があります。
認知症になりやすい人の特徴

認知症を早期発見するためには、認知症になりやすい人の特徴を知っておくことも必要でしょう。認知症になりやすい人の特徴に当てはまる場合、早期から予防対策をとり、認知症発症リスクを軽減することにも役立ちます。
ここからは、認知症になりやすい人の特徴について、性格・生活習慣・病気や怪我・遺伝的要素の4つの観点から解説します。
性格が神経質、怒りっぽい、頼るのが苦手
性格特性と認知症のリスクについて調べた研究において、「神経症傾向が強い人、協調性の低い人、誠実性の低い人」が認知症になりやすい傾向にあることが示されています。
これらの特徴を示す性格の例として、以下の3つが挙げられます。
- ・神経質
些細なことで落ち込んでしまったり、情緒が不安定であったりする人は、周囲の目を気にするあまり、他者との交流を避けて引きこもりがちになるでしょう。引きこもりがちな生活はうつ傾向を招きやすく、認知症を引き起こす可能性があります。 - ・怒りっぽい
怒りっぽい性格の人は、周囲から孤立しがちになり、コミュニケーションをとる機会が少なくなる傾向にあります。他者との関わりが減ることで脳への刺激も少なくなり、認知機能が低下することにつながります。 - ・頼るのが苦手
人に頼ることが苦手でなんでも一人でこなそうとする人は、元気に自立しているように見え、心配がいらないと思われがちです。しかし、自分一人でなんでもこなそうとすると、他人に助けを求めたり、自宅に誰かを招いたりする機会が減り、他者との交流の機会が少なくなりがちです。そのため、怒りっぽい人と同様、脳への刺激が少なくなり、認知症を招きやすくなるのです。
生活習慣の乱れ
生活習慣の乱れも認知症の発症の要因になる場合があります。
例えば、食生活の乱れは、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めます。
運動不足の生活が続くと、糖尿病、脂質異常症、高血圧を発症するリスクが高まります。これらの生活習慣病は、動脈硬化を進展させ、認知症の発症リスクを高めるとされています。
そのほか、喫煙やアルコールへの依存も認知症の発症を高めるリスク因子であるといわれています。
病気・怪我
先述したように、生活習慣病である糖尿病、高血圧、脂質異常症は認知症の発症リスクを高める可能性があります。ほかには、脳卒中、難聴、歯周病なども認知症の発症と関連性があるといわれています。
遺伝的要素
多くの認知症は、遺伝的要素に生活習慣や環境要因の影響が加わった結果として発症するため、認知症がそのまま遺伝することは稀です。
しかし、一部の家族性アルツハイマー型認知症は、特定の遺伝子変異が原因で発症することがわかっています。生活習慣などの影響を受けず、ある年齢に達すると認知症を発症するのです。このタイプの認知症では、2分の1の確率で子どもに遺伝すると考えられます。
全体でみれば認知症が遺伝するケースは稀ですが、心配な方は遺伝子検査や定期的な脳ドックを検討するとよいでしょう。
認知症の早期発見のために家族や自分ができる5つのこと

認知症は早期発見・早期治療が大切であることを解説しました。では、認知症の始まりのサインを見逃さないためには、どのような行動を心がければよいのでしょうか。認知症を早期発見するためにご家族やご自身ができる5つのことを紹介します。
家族との定期的な会話
認知症の初期症状として大切な「もの忘れ」の症状は、本人との会話で気付くケースが多いでしょう。認知症のサインにいち早く気付くため、ご家族との定期的な会話をこころがけましょう。
チェックリストの活用
認知症を疑う場合、チェックリストの活用も有効です。以下のチェック項目で3つ以上当てはまる場合、早めの受診が推奨されます。
- ・同じことを言ったり聞いたりする
- ・物の名前が出てこなくなった
- ・置き忘れやしまい忘れが目立ってきた
- ・以前はあった関心や興味が失われた
- ・だらしなくなった
- ・日課をしなくなった
- ・時間や場所の感覚が不確かになった
- ・慣れた所で道に迷った
- ・財布などを盗まれたという
- ・ささいなことで怒りっぽくなった
- ・蛇口・ガス栓の締め忘れがある、火の用心ができなくなった
- ・複雑なテレビドラマが理解できない
- ・夜中に急に起きだして騒いだ
出典:愛知県HP「認知症チェックリスト~早期発見・早期対応に向けて自分・家族で気づくヒント集~」
「もの忘れ外来」の受診
気になる症状がある場合、早めに「もの忘れ外来」を受診することをおすすめします。
まずはかかりつけ医に相談し、お住まいの地域のもの忘れ外来を紹介してもらうのもよいでしょう。かかりつけ医がいない場合は、役所の高齢福祉課などに相談することも可能です。
認知症検診を受ける
認知症の早期発見には「もの忘れ外来」の受診が有効ですが、受診に抵抗を感じる方もいるでしょう。そのような場合、健康診断の一環として「認知症検診」や「脳ドック」を受ける方法もあります。
一般的な人間ドックの中にメニューとして用意されていたり、オプション検査として追加したりできます。
認知症の疑いがある方の進行を抑える方法

認知症を早期発見するための方法や対策について解説してきました。では、認知症の疑いがある場合、進行を抑える方法はあるのでしょうか。認知症の進行を抑えるためには、以下の4つの方法を取り入れるとよいといわれています。
運動を取り入れる
近年の研究では、運動がアルツハイマー病の進行を防いだり、予防したりできるという報告があります。ウォーキングや軽いジョギングなど、有酸素運動を日々の生活に取り入れるとよいでしょう。
質の良い睡眠を確保する
睡眠も認知症の発症と関わりがあるといわれています。質のよい睡眠を確保できるよう、睡眠リズムを整え、ご自身にあったリラックス方法を取り入れるとよいでしょう。
好きなことを楽しく行う
読書や音楽、手芸、パソコン、家事などの知的活動は、脳への刺激になり、認知症の予防につながります。ご自身の好きなことを見つけ楽しく続けることは、脳への良い刺激となるでしょう。
ホモシステイン酸を抑制する
認知症の発症には、ホモシステイン酸という神経毒が関わっているといわれています。ホモシステイン酸は、ホモシステインという私たちの血中に存在するアミノ酸の一種が酸化されることで生成される物質です。
加齢とともに、ホモシステインの酸化を防ぐ酵素であるSOD(Superoxide Dismutase)が減少し、ホモシステイン酸が生成しやすくなるとされています。このSODの低下を補うためには、抗酸化サプリメントの摂取が有効でしょう。
まとめ:認知症の早期発見で生活に安心を

認知症を早期発見するためには、初期症状を理解し、ためらわずに適切な検査を受けることが重要です。
認知症の正確な診断には、MRIやPET検査などが有効です。認知症の検査は、もの忘れ外来などを受診するほか、人間ドックの一環として受けることも可能です。
検査を希望する際は、MRI やPETなどの検査機器があるだけでなく、検査画像を正しく読み取れる医師が在籍する病院を選ぶことをおすすめします。
また、認知症の進行を防ぐためには、生活習慣を見直したり、抗酸化サプリメントを摂取したりすることが有効です。ご自身に合った対策を取り入れてみましょう。
会員制メディカルクラブ「セントラルメディカルクラブ世田谷」では、高精度の検査機器を活用し、画像診断専門医による質の高い人間ドックをご提供いたします。
また、高度な予防医療や健康相談サービスなど、個人に合わせたより適切なアドバイスで、プライベートドクターとしてみなさまの健康をお守りします。
人生の資本である「健康」を維持したい方や、オーダーメイド医療を受けたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。