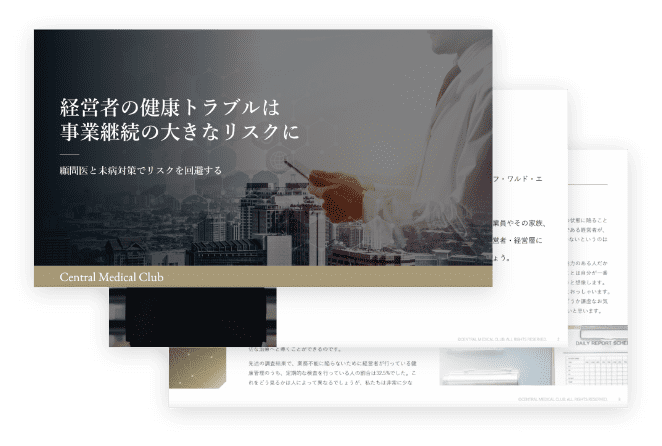未病とは?どのような状態なのか、症状や予防のポイントなど解説

日本が世界でも有数の超高齢化社会であることはすでにご存じのとおりですが、最新のデータでは、平均寿命が男性で81.09歳、女性は87.14歳(*1)、高齢化率は29.1%(*2)と、高齢化はいまだ上昇の一途をたどっています。
一方で人口は今後も減少が続き、2037年には高齢化率が33.3%にまで達し、3人に1人が65歳以上になると予測されています。(*2)
このような長寿社会のなかで注目を集めているのが「未病」という概念です。
本記事では、未病とは何かをご説明するとともに、その症状や予防のポイントについて詳しく解説していきます。
*1 参考:厚生労働省 簡易生命表(令和5年)
*2 参考:内閣府 高齢化白書(令和6年版)
未病とは?

未病とは、まだ病気を発症はしていないものの健康な状態からは離れつつある状態をいいます。「未(ま)だ病気ではない」というとらえ方もできますが、未病は明らかに「健康ではない状態」だということです。
ここでは、未病とは具体的にどのような状態を指すのか、厚生労働省と日本未病学会の定義をもとに解説していきます。
厚生労働省の定義する未病
厚生労働省では、未病を以下のように定義しています。
「健康と病気を二分論でとらえるのではなく、心身の状態は健康と病気のあいだを連続的に変化するものとして、このすべての変化の過程をあらわす概念」
さらに厚生労働省では、ビックデータやICTを活用したエビデンスに基づき、自分の未病の状態・将来の疾病リスクを数値であらわす「未病指数」の策定を推進しています。
その要件は以下のとおりです。
- 1.未来予測が可能であること
- 2.個別化されていること
- 3.連続的かつ可変的であること
- 4.使い易く費用対効果が高いこと
- 5.一定の科学的根拠があること
日本未病学会の定義する未病
日本未病学会では、以下のような状態をあわせて「未病」であると定義しています。
- ・自覚症状はあるが検査に異常がない
- ・自覚症状はないが検査に異常がある
一方で、「自覚症状があり検査にも異常がある」状態は「病気」であると定義されています。
なぜ未病が注目されているのか

冒頭で説明いたしましたように、日本では高齢化が進む一方で労働人口が減少しており、2037年には3人に1人が65歳以上になると予測されています。また、日本の平均寿命から考えると、65歳からさらに15年~20年の人生が残されていることになります。
そのため、健康で自立した生活を送り、長い老後のなかでも生活の質を維持・向上させていくことの重要性が取り上げられるようになってきました。厚生労働省のもと、未病対策を積極的におこなう自治体も年々増えており、超高齢化社会の大きな課題として未病が注目されています。
未病と予防医療の違い

未病と同じような場面で用いられる言葉として「予防」がありますが、未病と予防ではその意味が異なります。
予防とは、心筋梗塞や脳卒中・大腸がんなど、特定された疾患の発症を防ぐ意味で用いられます。
一方で、未病は心身全体の状態をあらわしており、たとえば「未病を治す」という場合は、心身全体を健康な状態により近づけることを意味します。
また、予防は臓器ごとに特定の疾患を治すことを目的とした西洋医学的な概念であり、未病は全身の「血・気・水」のバランスに注目した東洋医学的な概念であるという見方をすることもできます。
未病の予防が必要とされている理由

前項では、未病が注目を集めている背景として日本の高齢化があることを説明いたしました。そして現在、厚生労働省のもとでさまざまな予防対策が推進されています。
ここでは、なぜ未病の予防が必要とされているのか、その理由について解説していきます。
健康寿命を延ばすため
健康寿命とは、病気やそのほかの理由で制限されることなく、健康な状態で日常生活を送ることのできる期間を指します。
しかし、日本人の場合、平均寿命と健康寿命のあいだには約10年の差があります。超高齢化社会である日本において、一人ひとりの生活の質を維持して社会保障制度を持続させていくためには、健康寿命を延ばすことが必須であるといえます。
健康寿命を延ばすためには、未病とわかった段階で何らかの対策をおこない、病気が発症することを防ぐ必要があります。また、未病にならないための予防対策も同様におこなっていくことが求められています。
医療費・介護費削減への期待
日本は現在、高齢者(65歳以上)を生産年齢人口(15歳~64歳)が支える構図になっています。さらに高齢化が進んでいる現状を考えると、医療費や介護費が増大することによる財政破綻がないとはいいきれません。
病気を発症してから治療するのではなく、未病への対策により要介護状態や病気を防ぐことができれば、医療費や介護費の支出削減に期待ができます。また、65歳以上の高齢者でも健康で働くことができるようになれば、さらに医療費や介護費を削減することへとつながっていくかもしれません。
以上のことからも、日本の医療費・介護費の制度を持続可能にするためには未病の予防が大きなポイントになるといえます。
未病の症状

日本未病学会では、「自覚症状はあるが検査に異常がない」「自覚症状はないが検査に異常がある」という2つの状態をあわせて未病と定義しています。
では、具体的にどのような症状のときに未病だといえるのでしょうか。
【自覚症状はあるが検査に異常がない場合】
- ・食欲がない
- ・倦怠感がある
- ・よく眠れない
- ・めまいを感じる
- ・身体が冷える
- ・頭痛があるなど
【自覚症状はないが検査に異常がある場合】
- ・動脈硬化
- ・高脂血症
- ・脂肪肝
- ・肥満
- ・メタボリックシンドローム
- ・境界性高血圧
- ・境界性糖尿病
- ・高尿酸
- ・無症候蛋白尿
- ・無償校正脳梗塞
- ・潜在性心不全
- ・B型肝炎ウィルスキャリア
- ・骨粗鬆症
- ・インスリン抵抗性
以上のような症状が認められる場合、未病である、または未病の疑いがあると判断することができます。
未病を予防するためのポイント

ここからは、未病を予防するためのポイントを紹介していきます。
生活習慣を改善する
健康を損なうような生活習慣に心当たりがある場合、その習慣を改善することが大切です。未病の時点で、食生活・睡眠の見直しや適度な運動などの改善策を講じることで、病気の発症リスクを下げることができます。
食生活
腹八分目を心がけ、主食・主菜・副菜をバランスよく摂るようにしましょう。主食で糖質を摂取し過ぎると肥満の原因となるため、量には注意が必要です。また、塩分の摂りすぎは高血圧を引き起こす可能性があります。もし塩分を摂りすぎた場合は、カリウムが多く含まれる野菜・果物を食べることである程度対処できます。
適度な運動
未病の予防には、適度な運動も効果的です。コロナウィルスの流行以降はリモートワークの機会も増えているため、運動には意識して取り組む必要があります。
WHO(国連世界保健機関)では、1週間につき150分以上、中等度の運動をおこなうことを推奨しています。中等度の運動とは、やや息があがるものの会話はできる程度の運動を指します。やや早い速度でのウォーキング・ヨガ・筋トレなど、自分の環境や体力にあわせた運動を継続しておこないましょう。
良質な睡眠
質の良い睡眠を十分にとることも未病予防の重要なポイントです。睡眠が不足すると、食欲過剰を招くホルモンが分泌されることがわかっています。その結果、体重が増加して運動することも面倒になるという悪循環に陥り、メタボリックシンドロームをはじめとした未病を発症する可能性が高くなります。
良質な睡眠は健康であるために必要不可欠です。質の良い睡眠が得られていないと感じる場合は、生活習慣を見直す、就寝環境を整えるなどの工夫をしてみましょう。
未病のサインを見逃さない
未病には「自覚症状はあるが検査に異常がない」場合があることはすでにお伝えしてきました。しかし、自覚症状を見逃さないためには、自分の身体が発するサインに意識を向けることが必要です。
疲労感がぬけない、十分な睡眠がとれない、食欲がない、めまいや頭痛があるなど、些細なサインにも気を配るようにしましょう。もし、身体からのサインに気がついた場合は、そのまま放置するのではなく、かかりつけ医や病院で診察を受けることをおすすめします。
定期健診・人間ドックを欠かさない
未病には自覚症状がないこともあるため、最低でも年に一度は定期検診や人間ドックを受診して検査の数値をチェックするようにしましょう。
未病は、まだ病気ではないものの徐々に発症に向かっている状態です。定期健診や人間ドックの数値の変化から未病を発見できれば、病気の発症を防ぐための対策を講じることが可能になります。たとえば、病気を発症してしまった場合は病院での治療が必要となりますが、未病の段階であれば、食生活や運動などの生活習慣を見直すことで発症を回避することができるかもしれません。
また、未病の自覚症状は「だるい」「眠りが浅い」「食欲がない」「頭が重い」など、病気の症状だととらえるには軽いものが多いため、病院に行くまでもないと判断してしまうことも考えられます。そのような場合でも、年に一度の定期検診や人間ドックを必須としておけば未病を予防することができるでしょう。
シニア世代が特に注意すべきポイント
シニア世代には、特に注意するべき未病予防のポイントが3つあります。
ロコモティブシンドローム
運動機能の衰えにより要支援・要介護となるリスクの高い状態をいいます。ロコモティブシンドロームかどうかを判断するスクリーニング検査に「ロコモ5」があります。ロコモ5では、以下の簡単な5項目の質問から運動機能を評価します。
- ・階段の昇り降りができるか
- ・急ぎ足で歩くことができるか
- ・休まずにどのくらい歩けるか
- ・2 kg程度の重さの買い物をして帰ることができるか
- ・家のなかのやや重い仕事ができるか(例:布団の上げ下ろし、掃除機をかける)
フレイル
「活動的な生活が可能な状態」と「要介護状態」のあいだの状態を指します。フレイルになる前の軽い症状は「プレフレイル(前フレイル)」といわれていますが、ほとんどの場合で自覚症状がありません。また、フレイルはそのまま放置することで要介護状態になるリスクが高くなります。
オーラルフレイル
噛む・飲み込む・話すなど、口腔の機能が衰えることをいいます。オーラルフレイルによる口腔機能の衰退が食欲の低下やむせなどを引き起こし、全身の老化(フレイル)につながると考えられています。
以上の3つの症状は加齢によって引き起こされますが、いずれも未病の段階であるため、適切な対策をおこなうことにより改善が期待できます。かかりつけ医や歯科で定期的にケアを受け、生活習慣を見直すことで未病を防ぐことができるでしょう。
まとめ

今回の記事では、未病とは何か、その症状や予防のポイントなどについて詳しく解説してきました。
超高齢化社会を迎えている日本では、平均寿命と健康寿命の約10年の差を縮め、健康に生活できる期間を長くすることが課題として挙げられています。その対策のひとつとして、未病の予防があります。
未病とは、病気は発症していないものの健康からは離れつつある状態です。未病の段階でしかるべき対策を講じることができれば、病気の発症リスクを下げることが可能になります。
未病を予防するための具体的な対策としては、生活習慣の見直しや日頃から自分の身体のサインに意識を傾けることなどが挙げられます。なかでも、年に一度の定期検診や人間ドックで継続的に健康状態の変化をチェックすることは非常に重要です。
セントラルメディカルクラブ世田谷では、会員制医療サービスとして未病対策にも積極的に取り組んでおり、「0次予防」の実現を目指しています。
予防医療は以下の3段階に分かれています。
一次予防
生活環境・生活習慣の改善、健康教育などにより健康増進を図り、病気の発症を防ぐ
二次予防
早期発見・早期治療を促進し、病気の重症化を予防するための処置・指導をおこなう
三次予防
病気の発症後の機能回復や再発防止
セントラルメディカルクラブ世田谷が目指す0次予防は、一次予防よりも前段階にあり、地域や社会そのものが人を健康にできるよう整えることです。
そのために、まずは個々が定期的な検査で全身の状態をチェックし、その結果をもとに顧問医による健康管理をおこなうことで、未病や病気の発症を早いタイミングで検知することが必要といえます。
未病の早い段階でリスクを正しく把握し、適切な対策をおこなうことで健康寿命を延ばすことも可能になるでしょう。