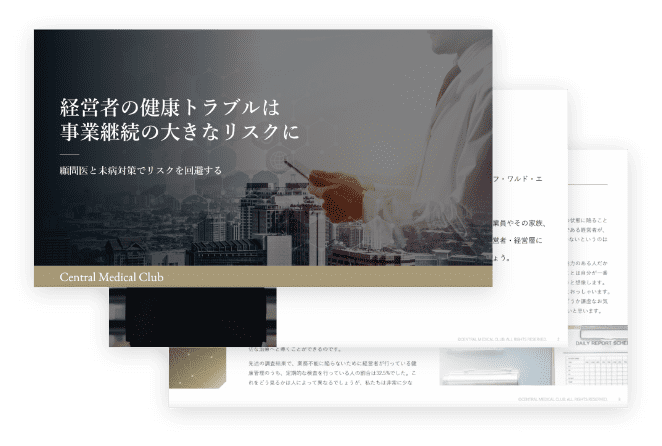個別化医療とは?メリット・デメリットや具体的な活用性など解説

近年、新たな医療の形として大きな期待を寄せられている個別化医療。従来は、同じ疾患であれば画一的な治療がおこなわれていましたが、個別化医療では患者さん一人ひとりの遺伝子などの特徴をもとに治療を選択します。個別化医療は、がん治療を中心に実用化が進んでいますが、今後ますますの発展が期待されているのです。
今回は個別化医療について、基本知識、メリット・デメリット、がんや難病における活用の具体例などを分かりやすく解説していきます。
個別化医療とは?基本知識について解説

個別化医療について、定義やこれまでの医療との違い、必要とされる背景について解説します。個別化医療とよく似た「プレシジョンメディシン」との違いについてもみていきましょう。
個別化医療の定義
個別化医療とは、患者さんの体質や病状に合わせておこなう治療のことです。患者さんの体質や病気にかかわる遺伝子・タンパク質を調べて、その特徴にあった薬を使用するというように、一人ひとりにもっとも適した治療をおこないます。
個別化医療は実用化が進んでおり、主にがん治療に対して活用されています。
これまでの医療との違い
これまでの治療は、同じ病名の患者に対して、画一的に治療がおこなわれていました。しかし、同じ治療をおこなっても、治療効果が得られる人と得られない人、副作用が起こりやすい人と起こりにくい人がいるなど、個人差が大きかったのです。個人差が起こる原因について研究が進み、遺伝子や特定のタンパク質がかかわっていることが分かりました。
個別化医療では、治療を始める前に遺伝子や特定の物質に対する検査をおこないます。その結果にもとづいて、効果が高く副作用のリスクが少ない薬を選んで投与するため、個人にとってベストな治療が可能となります。
個別化医療が必要とされる背景と現状
個別化医療は、一人ひとりの遺伝子情報や病状に合わせて、効果が高く副作用の少ない治療ができるため、さまざまな疾患の治療に広がりを見せています。不必要な治療を免れることで、結果的に医療費を抑えられたり、治療中も生活の質を維持したりすることが期待されているためです。
しかし、遺伝子情報を調べる検査は、実施できる施設が少ない・検査を受けるにあたって保険適用の制限がある・検査を受けても治療法が見つからないなど、個別化医療にはいくつかの課題があります。
個別化医療とプレシジョンメディシンの違いとは
個別化医療はPersonalized Medicineといい、患者一人ひとりを対象として、それぞれの病状や遺伝子に応じた治療をおこなうことです。
一方、プレシジョンメディシン(Precision Medicine)は「精密医療」と呼ばれています。疾患を引き起こす遺伝子や特定の物質など特徴にもとづいて、同じような性質を持つ患者さんをグルーピングし、その集団ごとに有用性の高い治療をおこないます。
個別化医療のメリット・デメリット
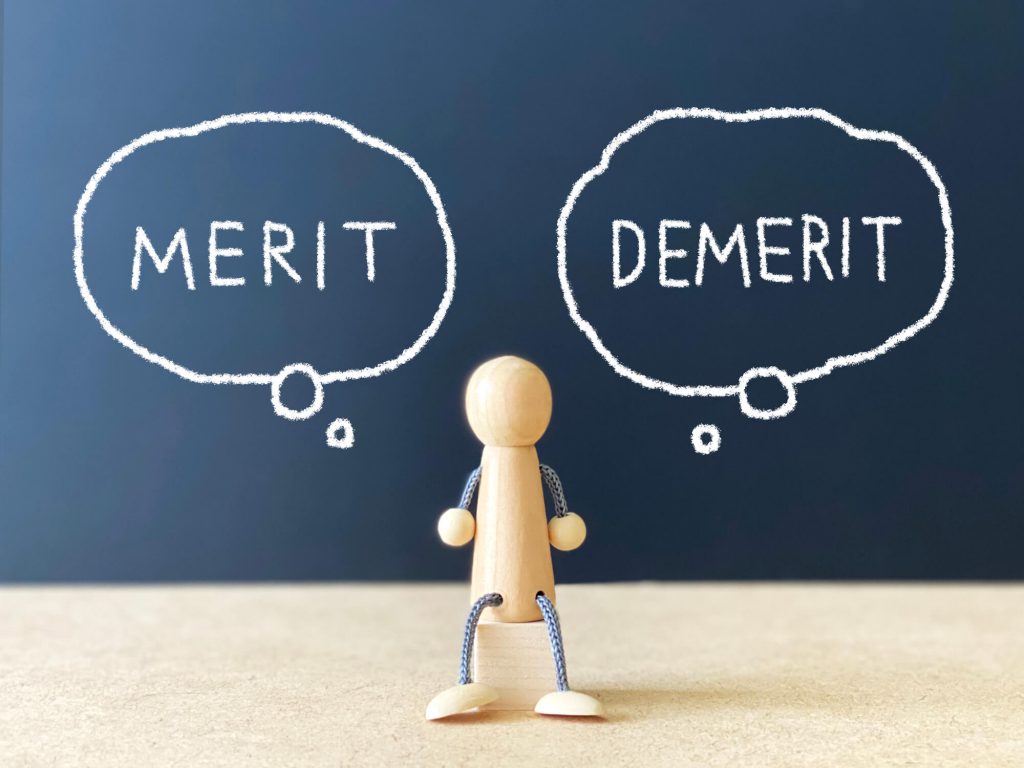
がんや難病などの治療で広がりつつある個別化医療の、メリットとデメリットについて確認しましょう。
個別化医療のメリット
個別化医療のメリットについて、3つのポイントに分けて解説します。
個々に合った効率的な治療
個別化医療では、治療を開始する前に疾患の原因となる遺伝子や特定の物質を調べて、異常があるかどうか確認します。異常が見つかれば、それに対応する治療方法を選ぶことが可能です。
治療のターゲットをあらかじめ絞ることができるため、合うかどうか分からない治療をくり返さずに済み、初めから自分に合った治療ができるメリットがあります。
副作用の発現リスクを低下
個別化医療において、遺伝子型を調べると、薬剤の代謝機能の違いも知ることができます。体質に合わない治療を避けたり、薬剤の投与量を調整したりすることで、副作用の発現リスクを減らすことが見込まれます。
社会復帰の早期実現
個別化医療をおこなうと、より効果が高く副作用の少ない治療を受けられます。そのため、治療にかかる期間が短くなり、早めに社会復帰ができることが期待されます。また、治療期間が短縮されると、精神的・経済的な負担も少なくなるでしょう。
個別化医療のデメリット
有益性の高い個別化医療ですが、現時点では課題も残されています。3つのポイントに分けてみていきましょう。
診断までに時間がかかる
個別化医療をおこなう上で欠かせない遺伝子解析検査は、診断が下りるまでに時間がかかります。
1回の検査で数十~数百個の遺伝子を解析する場合、1ヶ月半~2ヶ月ほどの時間を要します。病状によっては、遺伝子解析の結果が出る前に悪化してしまい、個別化医療を活かした治療を受けられないこともあるでしょう。
治療方法が見つからない可能性もある
検査を受けても、個別化医療の対象となる異常が発見されないことがあります。検査をおこなって、遺伝子や特定の物質に対する異常について情報が得られたとしても、対応できる治療方法が承認されていなかったり、薬剤を投与する条件に当てはまらなかったりすることもあるのです。
検査や治療に多額の費用がかかる
個別化医療にかかわる遺伝子検査は、保険適用されているものがありますが、受けられる条件が定められています。たとえば、多数の遺伝子を1度に調べる「がん遺伝子パネル検査」について、保険適用できるのは標準治療を終えた後に限られ、検査実施は1回のみと決められているのです。
がん遺伝子パネル検査を、保険適用されない期間に受ける場合は、検査費用が全額自己負担となり、検査によって40万円~100万円と高額です。
がん個別化医療を可能とする医薬品や検査方法

個別化医療は、現在がん治療において特に発展しています。がんの個別化医療において、使用されている医薬品や検査方法について解説していきましょう。
分子標的薬
分子標的薬とは、がん細胞の遺伝子や表面にあるタンパク質に対して作用する薬です。
従来の抗がん剤は、がん細胞のみならず健康な細胞も攻撃してしまうため、髪の毛が抜けたり、血液障害を起こしたりするなど日常生活に支障のある副作用が起こりやすくなります。
分子標的薬は、がん細胞が持つ特定の物質だけを選んで攻撃するため、効率よくがんの増殖を抑えられ、副作用発現リスクが大きく軽減されています。
コンパニオン診断薬
コンパニオン診断薬とは、患者さんへ特定の医薬品を投与したときに「治療効果が得られるか」「副作用は起こりにくいか」などを予測するために用いる薬です。コンパニオン診断薬を用いることで、特定の医薬品に対して有益性が見込まれる患者さん、前もって選別できるため、不要な治療をおこなわずに済む利点があります。
遺伝子パネル検査
遺伝子パネル検査とは、1度の検査でがんに関係する多数の遺伝子情報を調べられる検査です。遺伝子異常が見つかった場合、その異常に対して合う薬があるかどうか探す目的があります。がん遺伝子パネル検査には、保険適用されているものと自由診療で受けられるものがあります。
ただし検査を受けても、効果が見込める治療方法が見つからないこともたびたびあるのです。がん遺伝子パネル検査は、意図せず「生まれつきがんになりやすい遺伝子」を持っていることが判明する可能性があることも理解しておきましょう。
がん個別化医療の具体例

がん治療において、個別化医療がおこなわれている具体例を解説していきましょう。
乳がん
乳がんは、がん組織の性質の違いによって4つのサブタイプに分類されます。
- ・ホルモン受容体陽性・HER2陰性
- ・ホルモン受容体陽性・HER2陽性
- ・ホルモン受容体陰性・HER2陽性
- ・ホルモン受容体陰性・HER2陰性
日本人女性にもっとも多い「ホルモン受容体陽性、HER2陰性」の乳がんにおいて、正しく予後を見極めるために、遺伝子検査の「オンコタイプDX」がおこなわれています。乳がん再発にかかわる21個の遺伝子を解析して、再発リスクを数値化し、再発予防に抗がん剤の追加治療をおこなうかどうか検討するのです。
また、乳がんのなかには、遺伝性で発症するものがあります。遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)では、BRCA1またはBRCA2という遺伝子変異を持ちます。この遺伝子変異を持つ乳がんの治療には、分子標的薬のオラパリブが2018年に承認されています。
肺がん
肺がんを発症する原因遺伝子は、さまざまな種類があるため、遺伝子変異にもとづいた治療が必要です。非小細胞肺がんにおける遺伝子変異には、EGFR、ALK、ROS1、BRAF、NTRK、MEK、MET、RET、KRAS、HER2があり、それぞれに対する分子標的薬が存在しています。
しかし、それぞれの分子標的薬ごとにコンパニオン診断をおこなうと非常に時間がかかるため、数種類の治療薬について同時にコンパニオン診断できる肺がん遺伝子パネル検査が登場しました。がん遺伝子検査をおこなう際には、手術時の組織片・血液・がん細胞が含まれた胸水などが用いられます。
大腸がん
大腸がんの増殖にかかわる遺伝子に、RAS遺伝子があります。がん遺伝子検査をおこない、RAS遺伝子の変異があるかないかで治療薬が異なります。RAS遺伝子に変異がない場合は、抗EGFR抗体薬で治療をおこない、変異がある場合は、抗VEGF抗体薬にて治療をおこなうのです。
ほかにも大腸がんでは、MSI、BRAF、HER2などにも遺伝子異常が起きていることがあります。これらのがん遺伝子検査は保険適用されていますが、それぞれの遺伝子によって検査をおこなう時期が定められています。
胃がん
切除不能進行・再発胃がんで、全身化学療法をおこなう際に、がん遺伝子の特徴を調べてから使用する薬剤を決定しています。
主なコンパニオン診断には、HER2検査がおこなわれており、HER2陽性と診断されると分子標的薬の「トラスツズマブ」が使用されます。2024年3月には、がん細胞表面に出現するタンパク質CLDN18.2をターゲットとした分子標的薬の「ゾルベツキシマブ」が承認されました。ゾルベツキシマブは、コンパニオン診断をおこない、HER2陰性かつCLDN18.2陽性の場合に使用されるのです。
前立腺がん
遠隔転移のある去勢抵抗性前立腺がん(mCRPC)では、抗がん剤または分子標的薬の使用が検討されます。mCRPCでは、BRCA1およびBRCA2遺伝子に変異がみられるケースがあり、BRCA1/2遺伝子検査やFoundationOne® CDx がんゲノムプロファイルをおこなうのです。変異がみられるときは、分子標的薬の1つPARP阻害薬の「オラパリブ」や「タラゾパリブ」が投与されます。
がん以外の疾患における個別化医療の活用

がん以外の疾患においても、個別化医療が活用されています。具体例について紹介していきましょう。
二次性心筋症
二次性心筋症とは、アルコールやほかの疾患が原因となり心臓に障害が起こる状態です。
遺伝性ATTRアミロイドーシスやファブリー病などの遺伝性疾患では、二次性心筋症を発症することがあります。二次性心筋症の診断においては、原因となる疾患を判定するために、遺伝学的検査が重要です。
対象となる遺伝子変異が見つかった場合、遺伝性ATTRアミロイドーシスではsiRNA治療、ファブリー病ではシャペロン治療がおこなわれます。
原発性免疫不全症(PID)
原発性免疫不全症(PID)は、生まれつき免疫系のどこかに問題があり、感染症にかかりやすいなどの特徴がある病気です。
トラブルが生じる免疫細胞の種類によって、400以上の疾患に分類され、そのほとんどで原因遺伝子が分かっています。疾患により、現れる症状や重症度が異なるため、遺伝子検査をおこなうことが必須です。遺伝子変異の結果によって、一人ひとりにあった治療がおこなわれています。
まとめ

個別化医療は、がん治療を中心として飛躍的に発展しています。患者さん一人ひとりの遺伝子情報や病状に合わせて、効果が高く副作用の少ない治療が可能となり、早期の社会復帰も期待できます。現在はがんのみならず、二次性心筋症や原発性免疫不全症など、さまざまな疾患においても活用が広がっているのです。
遺伝子検査の診断に時間がかかること、高額な検査費用、検査を受けても治療法が見つからない可能性など、いくつかの課題は残されているものの、個別化医療は患者さんにとって今後さらに身近な医療になることが望まれています。
自分や家族ががんや難病などの疾患に直面した際は、もっとも適切な治療法を選ぶために、遺伝子検査などの個別化医療を積極的に活用しましょう。