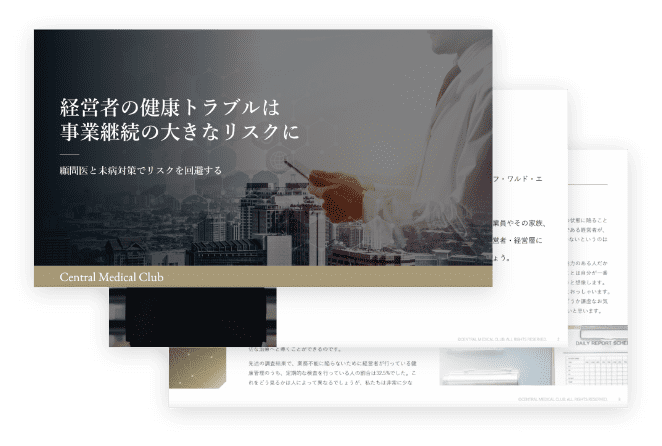セカンドオピニオンで何が得られるのか、どのように受けたらよいのか、注意点は
顧問医セカンドオピニオンは「第2の意見」という意味で、患者さんが主治医以外の医師に、病気の見解を尋ねる医療サービスです。
医療は日進月歩と言いますが、目覚ましい進歩を遂げ情報量も各段に増えました。そして高度に専門化され、それが結果として細分化を招きました。1人の医師は専門性を高度に研究できるようになりましたが、その結果、昨今の問題は、医師が診れる領域が狭まってきたということです。
専門化と細分化が進んだことにより、1つの分野に秀でた詳しいスペシャリストタイプの医師が増えました。
そのため、患者さんがセカンドオピニオンに上記のような医師を利用すれば、最善と思える治療法を選択できる可能性が高まります。とくにその分野のスペシャリストの意見を聞くことで、最新の診断や治療を受けられる可能性も高くなります。セカンドオピニオンは、効果的かつ効率的な医療の実現に欠かせなくなっています。
治療法の決定は患者さんにとって非常に重要な決断となるので、積極的にセカンドオピニオンを利用することをおすすめします。
この記事では、患者さんがセカンドオピニオンで得られるものを解説したうえで、セカンドオピニオンを受ける方法や注意点を紹介します。

納得して治療を受けるために
患者さんがセカンドオピニオンから得られる最大のメリットは、納得できる治療でしょう。
例えばある患者さんが、主治医からaという治療法を提案され、別の医師にセカンドオピニオンを求めたところ、その医師も治療aに賛同したとします。
このとき患者さんは「治療aなら問題なさそうだ」と納得することができます。
治療法に納得できると、患者さんは例え辛い治療であっても前向きにその治療を受けようという気持ちになります。
セカンドオピニオンには、これらの治療に対する姿勢以外の副産物もあります。
別の治療法を知ることができる
新しい医療器具や新薬が開発されたことで、1つの病気に対する治療法が増えました。これまで手術が必要だったものが放射線治療や薬で治るようになったり、入院が必要だったものが外来受診で済むようになったりしています。
たとえば主治医が患者さんに、2つの治療法を提示したとします。しかし患者さんが、そのどちらの治療も受けたくない場合、「第3の治療法はないのか」と考えたくなります。
そのときセカンドオピニオンを受けると、その医師が第3の治療法を提案してくれるかもしれません。
咽頭がんを例にとって考えてみましょう。
主治医から、1)手術による全摘出、2)抗がん剤治療の2つの選択肢を提示されたとします。
「もし自分だったら」と考えてみてください。
このようなとき「別の治療法はないのか」「他の医師も同じ意見なのだろうか」と思うはずです。
セカンドオピニオンを受ければ、3)放射線治療や4)遺伝子検査 5)遺伝子検査の結果に応じた分子標的薬の選択といった新たな情報が得られるかもしれません。
主治医と違う視点で意見をもらえる
セカンドオピニオンの医師が、主治医とまったく同じ見解を示すことは珍しくありません。
日本では通常、病気をすると保険診療の枠内で検査や治療を受けることになります。また、それぞれの治療におけるガイドラインなどがあり、「この病気にはこの検査とこの治療薬を使う」といった内容がスタンダードになっているため、保険診療を中心の病院でかつ同じ科目の医師であれば複数の医師であっても同じ見解を持つことのほうが多いといえます。
では、新しい意見を聞きたいときは、どのような医師に相談すればよいのでしょうか。
おすすめは、ドクターズドクターと呼ばれる医師に相談することです。その代表は、放射線科専門医です。
放射線科専門医は患者さんの全身を診るので、広い視野を持って検討することができ、複数の治療法を示すことができます。それで、医師が頼る医師(=ドクターズドクター)と呼ばれるわけです。
その他の診療科でも、ドクターズドクターや、セカンドオピニオンを得意にする医師がいて、その医師たちはなるべく多くの選択肢を出そうとしてくれるでしょう。
そして、それぞれの治療法について、メリットとデメリットを教えてくれるはずです。
病気と治療に詳しくなることができる
セカンドオピニオンを求める患者さんは、自分の病気と真剣に向き合い、病気や治療についてしっかり勉強する人が多い傾向にあります。
そして、セカンドオピニオンを求めれば、その患者さんは、主治医とセカンドオピニオン医の2人の医師から専門的な見解を聞くことができます。患者さんはますます病気と治療について詳しくなるでしょう。
主治医の力量や度量がわかる
セカンドオピニオンによって、主治医の治療方針に対して否定的な意見が得られるかもしれません。あるいは、主治医が提案する治療法より治療成績がよく、患者さんの体への負担が少ない治療法が提案されるかもしれません。
セカンドオピニオンによって、主治医の力量がわかることもあります。
また、最近は減りましたが、かつては、患者さんが主治医に「セカンドオピニオンを受けたい」と告げると、「自分の医療を信じないのか」と言わんばかりに露骨に嫌な顔をする医師がいたようです。
このような態度は正しいとはいえません。
ただし、最近では、医治療方針を伝えたときに医師から「セカンドオピニオンを受けてみますか」と提案される場面も増えてきています。
詳しい説明を聞くことができる
誰かに説明することを苦手だと思う人もいるように、病状や治療方針の説明が得意ではない医師もいます。
患者さんがもし主治医の説明をよく理解できない場合には同席している看護師に確認するのもいいと思います。もしくは、セカンドオピニオンを依頼した医師により詳しい説明を求めることができます。
異なる診療科の医師に意見を求める
セカンドオピニオンでは、主治医の専門領域外の医師に意見を求めることができます。
病気と診療科の関係は、「この病気はこの診療科で治療する」という関係がある一方で、「こちらの診療科でもあちらの診療科でもこの病気を治療する」という関係もあります。
異なる診療科の医師にセカンドオピニオンを求めると、病気を多角的に診てもらうことができます。
放射線科の医師にセカンドオピニオンを求める
がんの3大治療は、手術、抗がん剤、放射線といわれていますが、放射線を使ったがん治療は普及しているとはいえません(*1)。
そのため、がん患者さんの現在の主治医が、放射線治療に詳しくない可能性があります。
そこで、放射線科の医師にセカンドオピニオンを求めると、治療の選択肢が1つ増えるかもしれません。
画像診断を得意とする医師に診てもらう
医師は、CT検査やMRI検査、PET検査、組織検査の結果などで得られた画像をみて、治療方針を決めたり診断したり、病気の進行度を測ったりします。
医師のなかには、この画像診断を得意にしている人がいます。
画像診断が得意な医師にセカンドオピニオンを求めると、主治医とは異なる見解をしてくれるかもしれません。
画像診断は遠隔でも可能ですので、検査画像を送ることで、遠方の患者さんでもスペシャリストの診断を受けられる可能性があります。
受け方:主治医に「セカンドオピニオンを受けたい」と伝える
セカンドオピニオンを受ける方法は簡単です。主治医に「セカンドオピニオンを受けたい」と伝えるだけです。
患者さんが、「この医師のセカンドオピニオンを受けたい」という意中の医師がいれば、その名前を主治医に伝えてください。主治医は紹介状や診療情報提供書の作成、その他に血液検査や病理検査・病理診断などの記録、CTやMRIなどの画像検査結果などを準備して、患者さんに渡してくれます。
患者さんに意中の医師がいない場合でも、主治医にセカンドオピニオンの医師を推薦してもらうこともできます。患者さんが主治医に「先生が最も信頼できるお医者さんにセカンドオピニオンをいただきたい」と伝えてください。
セカンドオピニオンに必要な書類を手に入れたら、セカンドオピニオン医がいる医療機関に受診します。
セカンドオピニオンのあとは、主治医と相談して治療法を確定する
セカンドオピニオン医が、主治医の治療を強く支持すれば、もう一度主治医のところに戻って治療を継続することになるでしょう。
セカンドオピニオン医は患者さんに「主治医の治療方針は正しいと思います。信頼してよいでしょう」と励ましてくれるはずです。
セカンドオピニオン医が主治医と異なる見解を示したら、患者さんはどちらの医師に治療を依頼するか決めなければなりません。
セカンドオピニオンを受ける際の注意点
セカンドオピニオンはより精度の高い情報を得られますが、注意しなければならないこともあります。
ファーストあってのセカンドであることを忘れずに
セカンドオピニオンを受けるときの注意点は、ファーストオピニオン(主治医の見解)をまずはしっかり理解することです。
直感や感覚で「主治医の治療方針が納得できない」と判断しないようにしてください。
セカンドオピニオンを受けたいと思ったら、まずは、自分がなぜファーストオピニオンをすんなり受け入れることができないのかを考えてみてください。
主治医の説明でわからない部分があったら、もう一度しっかり質問してみましょう。主治医に直接聞きづらかったら、看護師に尋ねるという方法もあります。
ファーストオピニオンをしっかり理解したうえでセカンドオピニオンを受けないと、結局どちらの治療が自分にマッチしているのかわからなくなります。
セカンドオピニオンが、新たな混乱の種にならないようにしてください。
ドクターショッピングにならないように
ドクターショッピングとは、消費者が商品を品定めするように、患者さんが複数の医療機関にかかって医師を品定めする行為です。
セカンドオピニオンが、ドクターショッピングの1歩にならないようにしたいものです。
ドクターショッピング状態になると、患者さんは結局どの医師の意見が正解なのかわからなくなってしまいます。
そしてドクターショッピングは時間がかかるので、その間も病気が進行してしまう危険性があります。
セカンドオピニオンでも納得できない場合は、安易にサードオピニオンを求めて「第3の意見」を探すのではなく、主治医とセカンドオピニオンを依頼した医師の話をもう一度聞いたほうがよいでしょう。
まとめ~可能性を広げる
私たちCMCでは、患者さんに積極的にセカンドオピニオンをおすすめしています。
そのため当院は、国内外のさまざまな医療機関と提携し、当院の会員様にセカンドオピニオンを提供してもらっています。
セカンドオピニオンは治療の選択肢を広め、治療への納得度を高めます。また、最先端の医療を受けるチャンスも広げるでしょう。
後悔しない治療のために、セカンドオピニオンを有効に活用しましょう。