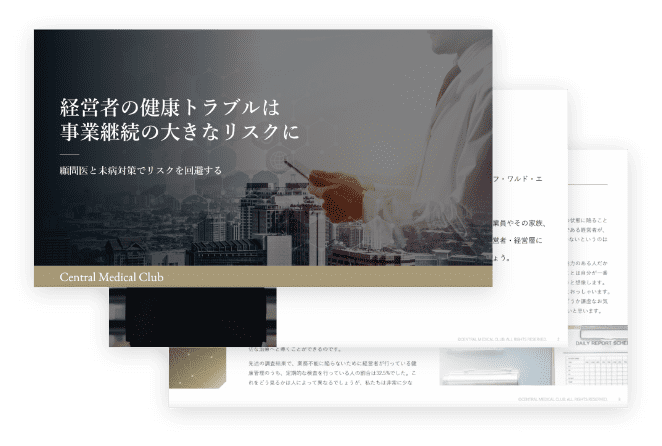がんになりやすい人の特徴は?予防・早期発見のための対策も解説

がんは日本人の死因上位を占める病気で、2人に1人が生涯で何らかのがんに罹患するといわれています。
がんは早期発見と治療が重要であるため、がんになりやすい人の特徴を知り、あらかじめ対策をしておけば、予防や早期発見に役立つでしょう。
今回はがんになりやすい人の特徴を紹介した上で、がんの予防・早期発見につながる対策を解説します。
がんになりやすい人の特徴9選

がん(癌)とは、細胞が遺伝子の傷などを原因として突然変異を起こし、「がん細胞」になることで発症する病気です。
健康な人でも毎日数千個のがん細胞が作られるといわれており、発生したがん細胞は免疫細胞によって排除されます。
しかし、何らかの要因で免疫細胞ががん細胞を排除できなくなると、がん細胞は無秩序に増殖を繰り返します。増殖したがん細胞の塊が悪性腫瘍(がん)となって、臓器を破壊したり、他部位に転移して増殖を続けたりといった身体への悪影響を及ぼすのです。
がん細胞が作られるメカニズムには、「細胞の遺伝子が傷付く」「免疫細胞ががん細胞を排除できなくなる」といった要因があり、がんのなりやすさは人によって違いがあります。
以下では、がんになりやすい人の特徴と、その理由や発症が懸念されるがん種を解説します。
喫煙をよくしている
喫煙習慣はがんのリスクを高めるといわれており、「喫煙をよくしている」ことはがんになりやすい人の特徴です。厚生労働省は、非感染性疾患と傷害による成人死亡の主要な決定因子の1つとして喫煙を挙げています。
参考:厚生労働省ホームページ「たばこの健康影響」
喫煙ががんのリスクを高める理由は、たばこの煙に多くの発がん性物質が含まれているためです。たばこを吸うと発がん性物質が肺から全身の臓器に運ばれ、遺伝子を傷付けることでがんのリスクを高めます。
1日の喫煙本数が多い、喫煙している年数が長い人ほど、がんになりやすいといわれています。
また、火の点いた先端から立ち上る副流煙にも発がん性物質は含まれており、受動喫煙もがんのリスクを高める点に注意してください。
喫煙によってなりやすいがんは下記のとおりです。
- ・鼻腔、副鼻腔がん
- ・口腔、咽頭がん
- ・喉頭がん
- ・食道がん
- ・肺がん
- ・肝臓がん
- ・胃がん
- ・すい臓がん
- ・子宮頸がん
- ・膀胱がん
飲酒量や頻度が多い
お酒に含まれているアルコールは、体内で「アセトアルデヒド」という物質に代謝されます。アセトアルデヒドは発がん性があるといわれており、飲酒量や頻度が多いことはがんになりやすい人の特徴です。
また、過度の飲酒は免疫機能の低下につながる点も、がんのリスクを高める要因です。他にも栄養摂取の偏りや、エストロゲン代謝に影響を及ぼすといったリスク要因も招きます。
過度の飲酒によってなりやすいがんは、主に下記の種類です。
- ・口腔、咽頭がん
- ・喉頭がん
- ・乳がん
- ・食道がん
- ・肝臓がん
- ・大腸がん
特に食道や喉頭はアルコールで粘膜が刺激を受ける部位であり、飲酒を原因とするがんのリスクが高いといわれています。
がんのリスクを上げる食品を多く食べている
アルコール類の他にも、がんのリスクになると言われる食品が存在します。がんのリスクを上げる食品とは、下記のような食べ物です。
| がんのリスクを上げる食品 | がんのリスクにつながる主な理由 |
| 牛・豚・羊などの赤身肉や加工肉 | ヘム鉄の酸化作用や、調理過程の焦げに含まれる発がん性物質の影響 |
| 塩蔵食品 | 塩分による胃粘膜への刺激や、塩蔵過程で生成されるニトロソ化合物の影響 |
| アルコール類、65℃以上の熱い飲み物 | 消化器の粘膜への刺激 |
ただし赤身肉や加工肉は、日本人の一般的な摂取量であれば影響が少ないという研究があります。塩蔵食品やアルコール類なども過剰摂取にならないよう注意しましょう。
がんのリスクを上げる食品を多く食べた場合は、下記のがんになりやすいとされています。
- ・口腔、咽頭がん
- ・喉頭がん
- ・食道がん
- ・肝臓がん
- ・大腸がん
運動をあまりしていない
運動をあまりしていないことも、がんになりやすい人の特徴です。運動は大腸がんや乳がんなどのリスクを下げるといわれています。
反対に運動をしていないと肥満になったり、インスリンの働きが低下して糖尿病になったりします。身体の免疫機能も働きにくくなり、免疫細胞ががん細胞を排除できなくなってがんのリスクが高くなるでしょう。
運動不足の方がなりやすいがんは、大腸がんの一種である「結腸がん」です。運動不足の状態では腸管の働きが悪くなって、便中に含まれる発がん性物質と腸粘膜が触れる時間が長くなり、がんのリスクが高くなります。
肥満や痩せすぎなど体型によるリスクがある
個々人で異なる体型も、がんのリスクにつながる可能性があります。
まずがんのリスクがある体型が「肥満」です。肥満になるとインスリンの過剰分泌が起きて高インスリン血症になり、大腸など消化器系のがんのリスクが高まるとされています。
女性の場合は脂肪組織からエストロゲンが産生されて、子宮体がんや乳がんのリスクが上がるともいわれています。
反対に、痩せすぎの場合もがんのリスクが上がる点に注意してください。痩せすぎの方は身体が低栄養状態にあるため免疫機能が低下していて、さまざまな種類のがんのリスクを高めます。
がんリスクが高い細菌・ウイルスに感染している
がんは生活習慣や体質的な問題だけではなく、感染症によって引き起こされるケースも少なくありません。国立がん研究センターによると、日本人のがんの約20%は感染症が原因とされています。
参考:国立研究開発法人国立がん研究センター「ウイルス・細菌感染とがん」
がんリスクにつながる細菌・ウイルスには、主に下記のものが挙げられます。
| 細菌・ウイルスの名称 | 感染により引き起こされる主ながん |
| 肝炎ウイルス(B型・C型) | 肝臓がん |
| ヒトパピローマウイルス | 子宮頸がん・陰茎がん・肛門がんなど |
| ヘリコバクター・ピロリ | 胃がん |
| ヒトT細胞白血病ウイルス1型 | 成人T細胞白血病・リンパ腫 |
| エプスタイン・バーウイルス | 上咽頭がん・リンパ腫 |
発がん性物質などの化学物質を扱う職場で働いている
発がん性物質などの化学物質を扱う職場で働いている場合は、化学物質に曝露することでがんのリスクにつながります。
化学物質などの人に対する発がん性はIARC(国際がん研究機関)が評価しており、2023年12月時点で128種類が「グループ1(発がん性がある)」に分類されています。たとえばアスベストやカドミウム、ベンゼンなどがグループ1に含まれる化学物質です。
化学物質への曝露では吸入経路となる鼻腔・喉頭・肺や、物質と接触する皮膚、排泄経路の尿路などにおいてがんのリスクが高まるといわれています。
ホルモン剤や抗ホルモン剤などを使用している
ホルモン剤や抗ホルモン剤は、乳がんや前立腺がんなどに対するホルモン療法で用いられる薬剤です。
しかし、ホルモン剤や抗ホルモン剤などを使用している場合、一部のがんのリスクを上げる可能性があります。がん治療などでホルモン療法を選択する場合は、担当の医師とよく相談して決めることが重要です。
がんのリスクを上げる主なホルモン療法としては、下記のものがあります。
| ホルモン療法の名称 | リスクが上がる主ながん |
| エストロゲン療法 | 閉経後の乳がん・子宮体がん・卵巣がん |
| エストロゲン・プロゲストーゲン合剤の経口避妊薬 | 肝臓がん・乳がん・子宮頸がん |
| エストロゲン・プロゲストーゲン合剤療法 | 閉経後の乳がん・子宮体がん |
| タモキシフェン療法 | 子宮体がん |
遺伝的な要因によるがんリスクがある
がんになりやすい人の特徴には、遺伝的な要因も挙げられます。遺伝的な要因とは、生まれつきで持っている遺伝子の変異(バリアント)のことです。
遺伝的な要因によってなるがんは「遺伝性潰瘍」と呼ばれます。遺伝性潰瘍は下記のようにいくつかの種類があり、どのようなバリアントがあるかによって発症しやすいがんが異なります。
- ・遺伝性乳がん卵巣がん
- ・リンチ症候群(大腸がん・子宮体がんのリスク)
- ・家族性大腸腺腫症
など
また、遺伝的な要因によるがんリスクがある方は、若年にもかかわらずがんになったり、他の人よりもがんに罹患しやすかったりする特徴があります
がんになりやすい人の特徴がある場合は予防・早期発見が重要

紹介した9個のがんになりやすい人の特徴は、個々の要因ががんリスクを上げるだけではなく、複数の要因が重なるとさらにリスクが高くなります。
がんになりやすい人の特徴に当てはまる方は、がんの予防・早期発見のために下記の対策を行いましょう。
過度の喫煙や飲酒を控える
喫煙・飲酒をどちらもしている方は、食道がんをはじめとして各種がんのリスクが高くなるという研究があります。がんの予防をするためには、過度の喫煙や飲酒を控えることが大切です。
また、受動喫煙にも肺がん・乳がんのリスクがあります。自分自身が吸わないだけではなく、他人のタバコによる受動喫煙も避けたほうがよいでしょう。
飲酒については体質的にアルコールの影響を受けやすい女性や、アルコールを分解する酵素の働きが弱い方のほうが、がんになるリスクが高くなるといわれています。アルコールに対する自分の体質も考慮して、飲酒量を調整してください。
喫煙や飲酒を完全に辞めることは簡単ではありませんが、まずは1日の摂取量や頻度を少なくする努力から始めましょう。
健康的な食生活を心がける
野菜・果物に含まれているビタミンや葉酸などの栄養素は、がんのリスク低下が期待できるといわれています。赤身肉・加工肉・塩蔵食品ばかりを食べず、野菜・果物も意識して摂取する健康的な食生活を心がけましょう。
特に塩分濃度が高い食べ物は、胃がんや高血圧のリスクを高めます。日本人の食事摂取基準を参考に、1日あたり男性は7.5g未満、女性は6.5g未満を目安に食塩摂取量を減らすとよいでしょう。
参考:厚生労働省ホームページ「ミネラル(多量ミネラル)」
また、食べ物や飲み物を熱い状態で食べると、口腔や胃の粘膜が傷付いてがんのリスクが高くなります。熱すぎる飲食物は食べやすい温度に冷ましてから食べてください。
日常的に身体を動かすことを意識する
運動をすると全身の血流がよくなり、体温が高くなって身体の免疫機能が向上します。腸管運動も活発になって大腸がんのリスクが低くなるため、日常的に身体を動かすことを意識しましょう。
仕事で忙しい方でも、1日に歩きかそれ以上の強度の運動を60分おこなうことがおすすめです。また1週間に60分は、息がはずんで汗をかくくらいの運動をしましょう。
ただし、過度な運動は身体に無理な負担がかかり、がんのリスクを高める活性酸素も体内で作られます。運動はウォーキング・ジョギング・水泳などの有酸素運動を選択し、身体に無理のない強度でおこなってください。
適正体重をなるべく保つ
肥満や痩せすぎはがんのリスクを高めるため、がんを予防するには適正体重をなるべく保つことが重要です。
適正体重とは、自分の身長に合う、病気になりにくいとされる体重のことです。自分の身長に下記の計算式を当てはめれば、自分の適正体重を算出できます。
【適正体重の計算式】
適正体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22
たとえば身長170cmの方の場合は、1.7m×1.7m×22=約64kgが適正体重です。
肥満や瘦せすぎの不安がある方は、現在の体重と適正体重を比較して、適正体重をなるべく保てるようにしましょう。
健康診断や人間ドックを受診する
がんの予防と早期発見をするには、健康診断や人間ドックを受診することが大切です。
健康診断や人間ドックを受診すると、各種検査を通して自分の健康状態を把握できます。細菌・ウイルスへの感染や発がん性物質の曝露、ホルモン剤などによる身体への影響も早期に分かり、対策しやすくなります。
特に人間ドックは病気の早期発見を目的としておこなう、総合的な精密検査です。身体の各部位に見られる不調などからがんの兆候を判断しやすく、がんの早期発見・治療につながることが期待できます。
まとめ
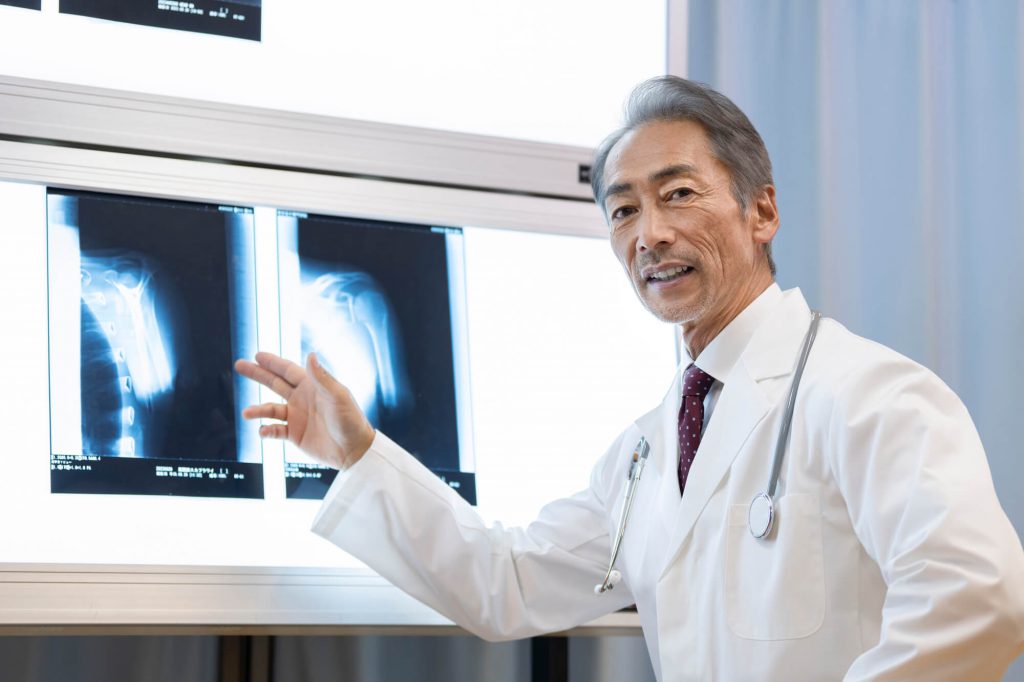
がんになりやすい人の特徴には、過度な喫煙・飲酒や運動不足といった生活習慣の他に、遺伝や仕事環境などの要因や、ホルモン剤の使用などが挙げられます。
がんになりやすい人の特徴に当てはまる人は、紹介した5つの対策を実践しましょう。健康的な生活習慣を身につけ、健康診断・人間ドックを定期的に受診することでがんの予防と早期発見ができます。
セントラルメディカルクラブ世田谷では、エグゼクティブ向けの人間ドックを提供しております。会社経営者でがんへの不安がある方、がん予防に興味がある方は、ぜひセントラルメディカルクラブ世田谷にお問い合わせください。