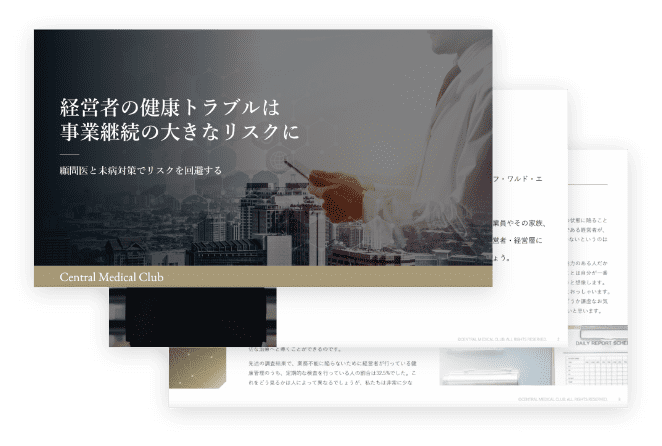アンチエイジングドック(抗加齢ドック)とは?検査項目やわかること、料金の相場など解説

人生100年時代といわれる今日において、 健康寿命を延ばすことが期待されているアンチエイジングドック。一般的な人間ドックとは異なるアプローチで、老化の進行度合いを科学的に測定します。現時点での体内年齢を知り、老化を促進する要因を特定することで、未病のうちから予防医療に取り組める点がアンチエイジングドック最大の特徴です。
今回はアンチエイジングドックについて、検査項目や受診のメリット、料金相場まで押さえておきたい情報をわかりやすく解説しましょう。
※本記事では参考情報としてご紹介していますが、当院では取り扱っておりませんので何卒ご了承ください。
アンチエイジングドック(抗加齢ドック)とは

アンチエイジングドックについて、基本知識や一般的な人間ドックとの違いなどを確認しましょう。さらに受診するのに適した年齢についても解説します。
アンチエイジングドックの概念
アンチエイジングドックは、病気の診断をおこなうものではなく、過剰に老化している部分を探し出して健康寿命を延ばすことを目指した検診です。
アンチエイジングドックでは、老化を引き起こす原因に着目して、加齢によるさまざまな健康トラブルを予測します。得られた検査結果をもとに、これまでの医療で積極的に取り組まれていなかったサプリメントやストレスケア・運動などの指導がおこなわれます。
加齢による影響を最小限に抑えるために対策をおこなうことで、長く健康的で質の高い生活を送れるようにするのです。
アンチエイジングドックと一般的な人間ドックの違い
アンチエイジングドックと一般的な人間ドックでは、アプローチや目的が異なります。
アンチエイジングドックは、老化・老化リスクを早期発見し、予防方法を提案します。健康な人に対して、病気や異常を呈する前からアプローチして予防医療をおこない、健康寿命を延ばしたり、生活の質を高めたりすることが目的です。
一般的な人間ドックは、病気を持っている人や健康状態が正常範囲から外れた人を検出します。病気を発症したり検査値に異常が見られたりする人に対して、早期発見・早期治療を行い、状態の悪化を防ぐことが目的です。
アンチエイジングドックが注目される背景
アンチエイジングドックは、健康寿命を延ばして平均寿命との隔たりを小さくするために注目されています。超高齢化社会の日本では、平均寿命と健康寿命に約10年ほどの差があり、医療費の増大や介護による負担が社会問題となっているのです。
アンチエイジングドックでは、従来の人間ドックでは発見できない老化度をチェックして、将来起こりうる健康問題に対して予防医療をおこないます。それにより、長く質の高い生活を維持できるようにすることが期待されています。
アンチエイジングドックを受けるのに適した年齢
アンチエイジングドックを受ける年齢に厳密な決まりはありません。ただし、海外の論文で44歳と60歳で急激に老化が進むことが報告されていることから、アンチエイジングドックを受け始めるのにもっとも適した年齢は40歳~45歳といえるでしょう。遅くとも55歳ごろまでには受診すると良いです。
ただし、年齢だけでなく個人の健康状態・家族歴・生活習慣などの要因も大きくかかわるため、どの年齢においても一度受診することをおすすめします。
アンチエイジングドックの主な検査項目とわかること

アンチエイジングドックでおこなわれる検査と、その検査によって分かることを解説しましょう。
老化度を判定する検査
老化度を判定する主な検査項目は、血管年齢・筋年齢・神経年齢・骨年齢・ホルモン年齢の5つがあります。それぞれについて詳しくみていきましょう。
血管年齢
血管年齢は、PWV検査や加速度脈波測定によって調べられます。
PWV検査は、腕と足首の脈を測定し、心臓から伝わる脈の速度を測定する検査です。加速度脈波測定は、指先の脈を測定し、その波形を数値化する検査になります。どちらの検査方法においても、調べて分かることは以下のとおりです。
- ●動脈の硬さや柔らかさ
- ●動脈硬化の進行度合い
- ●将来の心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスク予測
筋年齢
筋年齢は、体の筋肉量・体脂肪量・骨量・水分量・基礎代謝量など体組成計測と握力検査によって調べられます。検査によって分かることは以下のとおりです。
- ●筋肉量と筋力から算出される筋年齢
- ●実年齢と比較した筋機能の低下度
- ●サルコペニア発症リスクの予測
神経年齢
神経年齢は、ウィスコンシン・カードソーティングテストによって調べられます。前頭葉の機能を評価する検査で、考え方の柔軟性や問題解決能力などを見ます。調べて分かることは以下のとおりです。
- ●脳の認知機能の状態
- ●判断力・計画力・集中力など前頭葉機能の状態
- ●実年齢と比較した脳機能の老化度
- ●認知症発症リスクの予測
骨年齢
骨年齢は、DXA法や超音波法で骨密度を測定します。DXA法は、腰椎や足の付け根などの骨密度をX線の吸収率を利用して測定する方法です。超音波法は、かかとの骨に超音波をあてて伝わり方から骨密度を測定します。検査で分かることは以下のとおりです。
- ●骨密度から推測される骨年齢
- ●加齢による骨量減少の進行度合い
- ●将来の骨折や骨粗しょう症のリスク予測
ホルモン年齢
ホルモン年齢は、血液検査でIGF-I・DHEA-s・コルチゾールなどを測定し、加齢とともに変化するホルモンバランスを確認します。調べて分かることは以下のとおりです。
- ●ホルモンバランスの乱れの有無
- ●ホルモン分泌量の低下度合い
- ●体の機能低下のリスク予測
危険因子を判定する検査
老化を進行させる危険因子となるものは複数あります。それぞれの項目を判定する検査方法と調べて分かることについて解説しましょう。
免疫ストレス
免疫力の異常は老化の危険因子の1つです。免疫機能は、血液検査でリンパ球分類・DHEA-sなどを調べて評価します。調べて分かることは以下のとおりです。
- ●現在の免疫機能の状態
- ●免疫細胞のバランスの乱れ
- ●ストレスが免疫機能に与える影響
酸化ストレス
体内に過度の活性酸素が発生すると、体を酸化させて老化が促進します。酸化ストレスは血液検査において、活性酸素によるダメージの度合いをみるd-ROMsと、活性酸素に対抗する能力をみるBAPを測定することで分かります。検査によって分かることは以下のとおりです。
- ●体内の酸化ストレスによるダメージ度合い
- ●酸化作用に抵抗する力の程度
- ●酸化ストレスと抗酸化力のバランス
- ●将来の生活習慣病リスクの予測
心身ストレス
心身のストレスによって、さまざまな疾患を引き起こすことがあります。血液検査でコルチゾール/DHEA-s比を測定し、ホルモンの分泌状況を評価します。検査で分かることは以下のとおりです。
- ●自律神経のバランス状況
- ●ストレスに対する身体への影響
- ●うつ病など精神疾患の発症リスクの予測
糖化ストレス
体内にある余分な糖とタンパク質が結びつくとAGEs(終末糖化産物)という老化物質が作られ、さまざまな臓器に蓄積し疾患リスクが高まります。皮膚に光をあてるAGE Readerや血液検査で評価できます。検査によって分かることは以下のとおりです。
- ●体内の糖化ストレスの度合い
- ●血管の老化度
- ●肌・骨・髪などの老化度
- ●動脈硬化・糖尿病・がん・アルツハイマー型認知症など疾患リスクの予測
アンチエイジングドックを受診するメリット

アンチエイジングドックを受診するメリットを3つのポイントに分けて解説しましょう。
老化リスクを早期に発見できる
アンチエイジングドックでは、体内の老化度を把握し、加齢による健康リスクを発見できることが期待されています。筋肉・血管・神経・ホルモン・骨の状態を検査し、どの部分が年齢に対して老化が進んでいるかが明らかになるため、対策をおこなうべき部分がわかるようになります。一般的な人間ドックとは異なり、病気の予防ではなく、身体機能の老化の程度を測定し、加齢による影響を最小限にすることに重点を置いているのです。
予防医療に取り組める
アンチエイジングドックは、病気が発症する前にリスク因子を把握し、早期に対策を講じることを目的としています。検査結果にもとづいて、食事・運動・睡眠などの生活習慣の改善やサプリメントの摂取などをおこない、生活習慣病や過度な老化に関連するリスクを減らして、健康的な生活をより長く送ることが期待できます。
個別化された生活改善指導が受けられる
アンチエイジングドックでは、検査結果に基づいて個々の健康状態に適した生活習慣の改善策について、医師から提案を受けられます。弱点となっている箇所から改善をおこない、全体的なバランスを整えるようにしていくのです。
運動・食事管理・ストレス管理が含まれ、健康的に年齢を重ねるための具体的なアドバイスが得られます。酸化ストレスや糖化ストレスへの対策もおこなわれ、必要に応じてサプリメントや薬物治療も取り入れられることもあるでしょう。
アンチエイジングドックの料金相場と受診の流れ

アンチエイジングドックについて、コースごとの料金相場を確認しましょう。また受診の流れについても解説します。
検査コースと料金相場
アンチエイジングドックの料金は、一般的に15,000円から18万円程度の幅があり、検査内容によって異なります。
| コース | コース内容 | 料金相場 |
| 基本コース |
|
2万円~4万円 |
| 標準コース | 基本コースに加えて、ホルモンや老化危険因子を調べる項目数が増える | 7万円~8万円 |
| 詳細コース | 標準コースに加えて、画像検査・遅延型フードアレルギー検査・腸内フローラ検査などがおこなわれる | 15万円~18万円 |
受診の流れ
アンチエイジングドックを受診する際の大まかな流れは以下のとおりです。
| ステップ | 詳細 |
| 1.予約 | 複数のコースから、自分の希望するものを選択する |
| 2.検査当日 |
|
| 3.結果の説明 |
|
| 4.継続的なフォローアップ | 状況に応じて、3ヶ月~1年ごとに再検査をおこない、改善状況を確認する |
アンチエイジングドックに関するよくある質問

アンチエイジングドックに関する疑問点について、Q&A方式で解説しましょう。
アンチエイジングドックの検査結果をどのように活かしたら良いか?
アンチエイジングドックの検査結果は、現時点での体の老化度を評価するものです。結果を受けて、自分の弱点(老化が促進している点)を理解しましょう。
アンチエイジングドックでは、検査結果の説明とともに医師によるカウンセリングがあり、具体的なアドバイスが受けられます。アドバイスをもとに、食事・運動・ストレス管理など基本的な生活習慣改善に取り組むと良いです。必要に応じて、サプリメントや点滴治療などが取り入れられることもあります。改善状況を確認するために、定期的に再検査を受けることも大切です。
一般的な人間ドックとアンチエイジングドックは併用しても良いか?
一般的な人間ドックとアンチエイジングドックを併用すると、お互いに検査範囲をカバーできる利点があります。一般の人間ドックでは身体に病変がないかを確認し、アンチエイジングドックでは老化の進行状況を把握できます。併用によって病気を発症しているかどうかだけではなく、将来的なリスクも一緒に知ることが可能です。
また、一般的な人間ドックで異常が見つからなくても、アンチエイジングドックで老化による機能低下が指摘されることがあり、病気を未然に防ぐ対策に取り組めるのです。
アンチエイジングドックはどのくらいの頻度で受けると良いか?
アンチエイジングドックの受診頻度は、個人の年齢・健康状態・検査結果によって異なります。過度な老化がみられない場合は、食事・運動・ストレス管理など基本的な生活習慣の改善をおこない、1年ごとに受診すると良いでしょう。
基本の生活習慣の改善に加えてサプリメント摂取をおこなった場合は、6ヶ月後に再検査して変化がみられたか確認することをおすすめします。さらに薬物療法をおこなった場合は、3〜4ヶ月ごとに血液検査をおこない、数値の改善がみられたか確認しましょう。
まとめ

アンチエイジングドック(抗加齢ドック)は、一般的な人間ドックとは異なり、老化の進行度合いを視覚化して、未病の段階から予防医療に取り組むことを目的とした検診です。血管年齢・筋年齢・神経年齢・骨年齢・ホルモン年齢などの検査を通じて体内年齢を把握し、老化促進の要因を特定できます。
従来の医療ではあまり積極的におこなわれていないサプリメントやストレスケアの指導がある点が特徴です。40代前半からの受診が推奨され、料金は検査内容に応じて数万円〜十数万円の幅があります。健康寿命を延ばして質の高い生活を長く送るために、アンチエイジングドックの受診を検討しましょう。