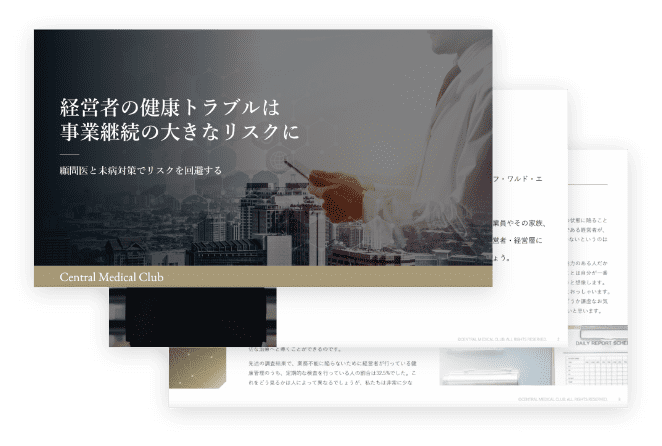【ビジネスパーソン必見】脳の老化を防ぐには?食べ物や生活習慣など解説

仕事に精力的に取り組むビジネスパーソンの中には、脳の老化が気になり始めている方も多いのではないでしょうか。年齢を重ねるにつれて脳の老化は進み、もの忘れなどの症状によって仕事に悪影響を及ぼします。
脳の老化を防ぐには、毎日の食事から摂取する栄養素や、運動・睡眠などの生活習慣に気を付けるとよいでしょう。
本記事では、脳の老化を防ぐためにビジネスパーソンの方が意識して摂りたい食べ物や、取り入れるべき生活習慣を解説します。
脳の老化とは?
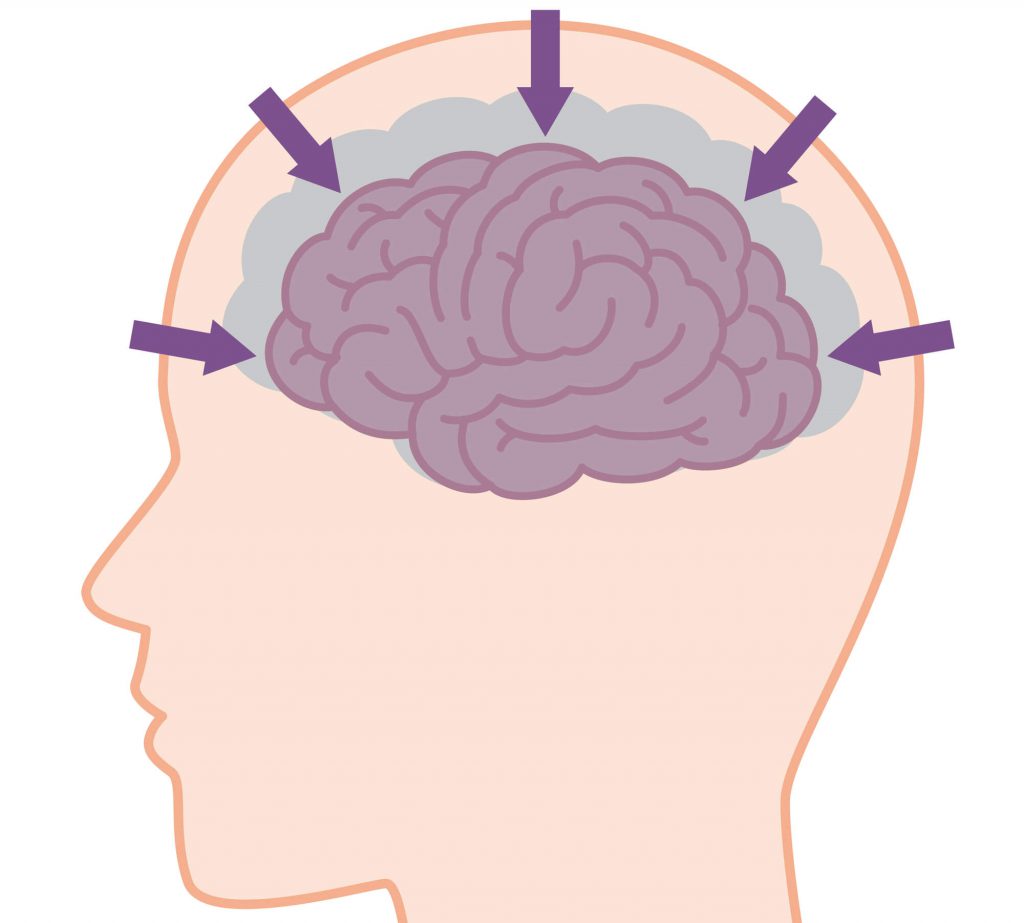
脳の老化とは、脳を構成する神経細胞が減って脳の容積・重さが減少し、記憶力や判断力の低下する減少です。脳の老化が発生する主な原因は加齢であり、誰にでも起こり得ます。
脳の重さは一般的に、成人で1,200~1,400gです。成人後は脳の容積・重さが維持されるものの、50歳頃を境に脳の萎縮が始まり、90歳頃には60歳頃よりも脳の重さが5~7%程度軽くなるとされています。
長く現役でいたいと考えるビジネスパーソンにとって、脳の老化は注意すべき現象です。
脳の老化によって現れる主な影響・症状
脳の老化によって現れる主な症状が「もの忘れ」です。
もの忘れとは、覚えた内容を後から思い出せない状態を指します。「前にも会ったことのある人の名前が出てこない」「物をどこに置いたか思い出せない」などがもの忘れの例です。
また、もの忘れには日常生活や仕事に支障を来たす「病的なもの忘れ」があります。「自分がやったことを忘れてしまい、周りの人に言われて知る」という経験がある方は、病的なもの忘れの可能性に注意したほうがよいでしょう。
さらに脳の老化が進むと「認知症」の症状が現れることもあります。
認知症とは、脳の認知機能が障害されることによって日常生活に支障を来たしている状態のことです。認知症の症状の1つに病的なもの忘れがあり、他にも下記のような症状があります。
| 症状 | |
| 失語 | 読む・書く・話す・聞くという言語機能が障害されて、文章を読めなくなったり、人の話が分からなくなったりする。 |
| 失行 | ネクタイの結び方が分からなくなったり、ペンの持ち方が分からなくなったりなど、今まで出来ていたことが急にできなくなる。 |
| 失認 | 現在の時間や場所が分からなくなったり、自分が何をしているかを思い出せなくなったりする。 |
脳の老化が必ずしも認知症につながるとは限らないものの、もの忘れや認知症のリスクを減らすためには脳の老化への対策が必要です。
脳の老化防止に役立つ食べ物・栄養素8選

脳はエネルギーとなるブドウ糖をはじめ、神経伝達物質の原料となる動物性タンパク質やビタミン・ミネラル類といった栄養素を消費して機能しています。脳の機能維持につながる食べ物を摂ることは、脳の老化を防ぐ対策法のひとつです。
以下では、脳の老化防止に役立つ代表的な栄養素と食べ物を紹介します。
【動物性タンパク質】肉・魚・卵をなるべく加熱せずに食べる
動物性タンパク質には「トリプトファン」という必須アミノ酸が豊富に含まれています。
トリプトファンは、心の安静を保つ神経伝達物質である「セロトニン」や、睡眠・覚醒のリズムを調整する「メラトニン」の原料となる物質です。肉・魚・卵といったトリプトファンが豊富な動物性タンパク質を食べることで、脳の活動に必要な神経伝達物質を作り出しやすくなります。
トリプトファンは熱に弱い性質があるため、動物性タンパク質からトリプトファンを摂取したいときはなるべく加熱せずに食べましょう。肉類は基本的に加熱調理の必要があるものの、魚の刺身や魚卵などの加熱せずに食べられる食品を選ぶと、効率よくトリプトファンを摂取できます。
【ビタミンB群】魚や魚卵、レバーから摂取する
ビタミンB群は下記の水溶性ビタミンの総称で、タンパク質・糖質・脂質の代謝にかかわる栄養素です。
- ●ビタミンB1
- ●ビタミンB2
- ●ビタミンB6
- ●ビタミンB12
- ●ナイアシン
- ●パントテン酸
- ●葉酸
- ●ビオチン
ビタミンB群をバランスよく摂取することで身体がエネルギーを生成しやすくなり、脳の効率的なエネルギー補給にもつながります。牛・豚・鶏のレバーや、マグロ・カツオなどの魚類がビタミンB群を豊富に含む食品です。
なかでもビタミンB6は、セロトニン・ドーパミン・ギャバなど神経伝達物質の合成を助ける役割があります。
脳の老化が気になる方は、ビタミンB6が豊富な赤身肉・牛レバー・マグロ・カツオ・バナナなどの食品を意識して食べるとよいでしょう。
【ビタミンE】アーモンドなどのナッツ類を食べる
ビタミンEは脂溶性ビタミンの1種で、強い抗酸化作用がある物質です。体内の脂質や脂溶性成分を酸化から守る役割があり、摂取することで脳の機能維持と老化防止につながる効果が期待できます。
ビタミンEが豊富な食品はナッツ類です。特にアーモンドは、ビタミンEの中でも生理作用が強いα-トコフェロールの成分量が多く、100gあたり30mgのα-トコフェロールを含んでいます。
参考:食品成分データベース「種実類/アーモンド/乾 – 01.一般成分表-無機質-ビタミン類」
他にも緑黄色野菜や植物性油脂、魚類もビタミンEが豊富な食品です。
さまざまな食品をバランスよく摂りつつ、間食にナッツ類を選ぶことでビタミンEを十分に摂取できるでしょう。
【鉄分】レバーなどのヘム鉄を摂取できる動物性食品を摂取する
鉄分は血液中のヘモグロビンの生成に必要なミネラルであり、セロトニンやドーパミンといった神経伝達物質を作る際にも欠かせない物質です。
鉄分を十分に摂取すると、ヘモグロビンによって脳内に十分な酸素が供給されると同時に、神経伝達物質が作られやすくなって脳の機能を維持できるようになります。
食事から鉄分を摂取するときは、「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の違いを把握しておきましょう。
ヘム鉄は動物性食品に多い鉄分であり、植物性食品に多い非ヘム鉄よりも体内での吸収率が高いという特徴があります。そのため、鉄分を摂取するにはヘム鉄を豊富に含む牛・豚・鶏レバーや赤身肉、魚介類などを意識して食べることがおすすめです。
一方で、非ヘム鉄もタンパク質やビタミンCと一緒に摂取すれば吸収率が高まる特徴があります。豆類や野菜類から鉄分を摂取するときは、一緒に肉類やビタミンC豊富な野菜・果実類を食べるとよいでしょう。
【n-3系脂肪酸】サバやイワシなどの青魚を意識して食べる
n-3系脂肪酸(オメガ3脂肪酸)は「α-リノレン酸」「EPA」「DHA」をまとめた総称で、体内では合成できない必須脂肪酸の1種です。中でもDHAは脳の発達や機能維持に効果が期待できる成分として知られています。
DHAが豊富な食品はイワシ・サバなどの青魚です。青魚はEPAも豊富に含んでいて、EPAは中性脂肪の生成や動脈硬化を抑制する効果が期待できます。
また、α-リノレン酸は体内でDHAに変換される物質です。α-リノレン酸を多く含む食品にはアマニ油・ナタネ油やクルミが挙げられます。
【アントシアニン】ベリー類は抗酸化物質を豊富に含んでいる
アントシアニンは植物に含まれる天然の色素で、強い抗酸化作用を持つ物質です。活性酸素を抑える抗酸化作用の働きにより、脳の老化や認知機能の低下を防ぐ効果が期待できます。
アントシアニンが豊富な食品は、ブルーベリー・ブラックベリーなどのベリー類や、ブドウ・ナス・黒豆・赤ジソといった赤~紺色が強い野菜です。
また、アントシアニンは摂取してから作用までの時間が早いものの、体内に留まりにくい性質があります。効果を得るには継続的に摂取することを心がけましょう。
【テオブロミン】カカオ含有量が高いチョコレートを選ぶ
テオブロミンは主にカカオ豆に含まれるアルカロイドの1種で、強い抗酸化作用があるとともに、動脈硬化や高血圧の予防効果があるといわれている物質です。
また、セロトニンをサポートする働きがあり、自律神経の調整を促す効果も期待できます。
テオブロミンを効率的に摂取するには、カカオ含有量が高いハイカカオチョコレートを意識して食べることがおすすめです。ハイカカオチョコレートはテオブロミンの含有量も高く、脳の機能維持の効果を期待しやすくなります。
【レシチン】大豆製品を食べると脳の機能維持が期待できる
レシチンはリン脂質の1種で、脳神経や神経組織を構成する重要な物質です。摂取したレシチンは「アセチルコリン」という神経伝達物質の材料にもなり、レシチンを十分に摂取することで脳の記憶や学習に関する働きが活性化するといわれています。
レシチンが豊富な食品は大豆製品や卵です。毎日の献立に味噌汁・豆腐・豆乳といった大豆製品や卵料理を加えることで、レシチンを摂取しやすくなるでしょう。
脳の老化を防ぐために実践したい生活習慣6選

脳の老化を防ぐためには、毎日の生活習慣の改善に努めることも大切です。
生活習慣は脳の健康と深くかかわっていて、健康的な生活習慣や脳を活性化させる活動を行うことで脳の老化防止が期待できます。
忙しいビジネスパーソンの方も、以下で紹介する生活習慣をなるべく実践するとよいでしょう。
さまざまな食品をバランスよく食べる
脳は多くの栄養素を消費する臓器であり、特定の栄養素のみに偏ると十分なパフォーマンスを発揮できなくなります。老化防止に役立つ食べ物で紹介した食品を中心に、さまざまな食品をバランスよく食べることを意識してください。
食事の基本的な献立は、炭水化物を中心とする「主食」とタンパク質・脂質を含む「主菜」、ビタミン群やミネラル類が豊富な「副菜」で構成することが大切です。
また、食事を抜くと脳に届く栄養素が不足するため、忙しいときであっても食事は3食きちんと摂るようにしましょう。
運動習慣を作る
スポーツやストレッチなどの定期的に身体を動かす習慣をつくると、全身の血流が良くなって脳にも酸素が送られやすくなります。
運動には脳が刺激されて認知機能が向上する効果もあるため、脳の老化防止のために運動習慣はぜひとも取り入れたい対策です。
特におすすめの運動が、ウォーキング・ジョギング・サイクリング・スイミングといった有酸素運動です。1日30分程度の軽い有酸素運動でも、脳を活性化させる効果があると言われています。
忙しくて運動する時間がない方は、日常動作の中で身体を動かすことを意識しましょう。
「エレベーターではなく階段を使う」「休憩時間に軽くスクワットをする」といったように、少しでも身体を動かす習慣を付けることで脳の老化防止につながる効果が期待できます。
適切な睡眠時間を確保する
睡眠中の脳では、老廃物・有害物質の除去や脳神経細胞(ニューロン)の新生がおこなわれています。睡眠時間が短い状態では老廃物などの除去やニューロンの新生が十分におこなわれなくなるため、適切な睡眠時間を確保することが重要です。
1日あたりの理想的な睡眠時間は7~8時間程度と言われています。現在の睡眠時間が短すぎる方は意識的に睡眠時間を確保しましょう。
飲酒は控えめにする
飲酒は脳の認知機能を低下させる要因であり、脳の萎縮につながるリスクもあります。
特に高齢期に近い方は、「年齢に伴う脳の萎縮」が起きているところに「飲酒での脳の萎縮」の相乗効果により、認知症のリスクが高まる点にも注意してください。
脳の機能を維持するためには、過度の飲酒を避けるようにしましょう。
厚生労働省によると、酒類の適量は1日あたり純アルコール換算で20g未満とされています。日本酒であれば1合以内、アルコール度数5%のビールであれば500ml以内が目安です。
参考:厚生労働省ホームページ「アルコール」
喫煙量の抑制か禁煙をする
慢性的な喫煙は脳の血流量を低下させる要因であり、脳の健康状態の悪化につながります。
特に喫煙と過剰な飲酒の両方を行っていると認知症のリスクを高めるといわれているため、喫煙・飲酒の習慣がある方は注意が必要です。
また、喫煙をする人は喫煙しない人に比べて、記憶・言語・認識といった機能をつかさどる「大脳皮質」が薄くなりやすいともいわれています。脳の老化を防ぐために、まずは喫煙量を減らすことから始めて、可能であれば禁煙をすることがおすすめです。
コミュニケーションの機会を増やす
人とのコミュニケーションには「考えて言葉を発する」「相手の発言を聞いて理解する」などの複雑なプロセスがあり、コミュニケーションの機会が多いほど脳の活性化が期待できます。
リモートワークで人とコミュニケーションを取る機会が減っている方は、意識してコミュニケーションの機会を増やすことが大切です。
特に初対面の方や世代が異なる方と会話をすると、脳に新しい刺激を与えられて認知機能の向上が期待しやすくなります。なるべくさまざまな方とコミュニケーションを取り、脳の活性化につなげましょう。
まとめ

脳の老化が進行すると、もの忘れや判断力の低下によって仕事に悪影響を及ぼすおそれがあります。ビジネスパーソンの方は、紹介した食べ物の摂取や生活習慣を取り入れて、脳の老化防止に努めましょう。
ビジネスパーソンは身体が資本です。現役として走り続けるためには、健康を維持することが何より重要となります。
多忙な日々のなかで効率よく健康管理をするには、日常生活でのケアを心がけるほか、会員制の医療サービス(メディカルクラブ)を活用するのもおすすめです。
セントラルメディカルクラブ世田谷では、エグゼクティブ向けの人間ドックや顧問医サービスをはじめとした予防医療を提供しております。
サービス内容について興味のある方は、お気軽にご相談ください。